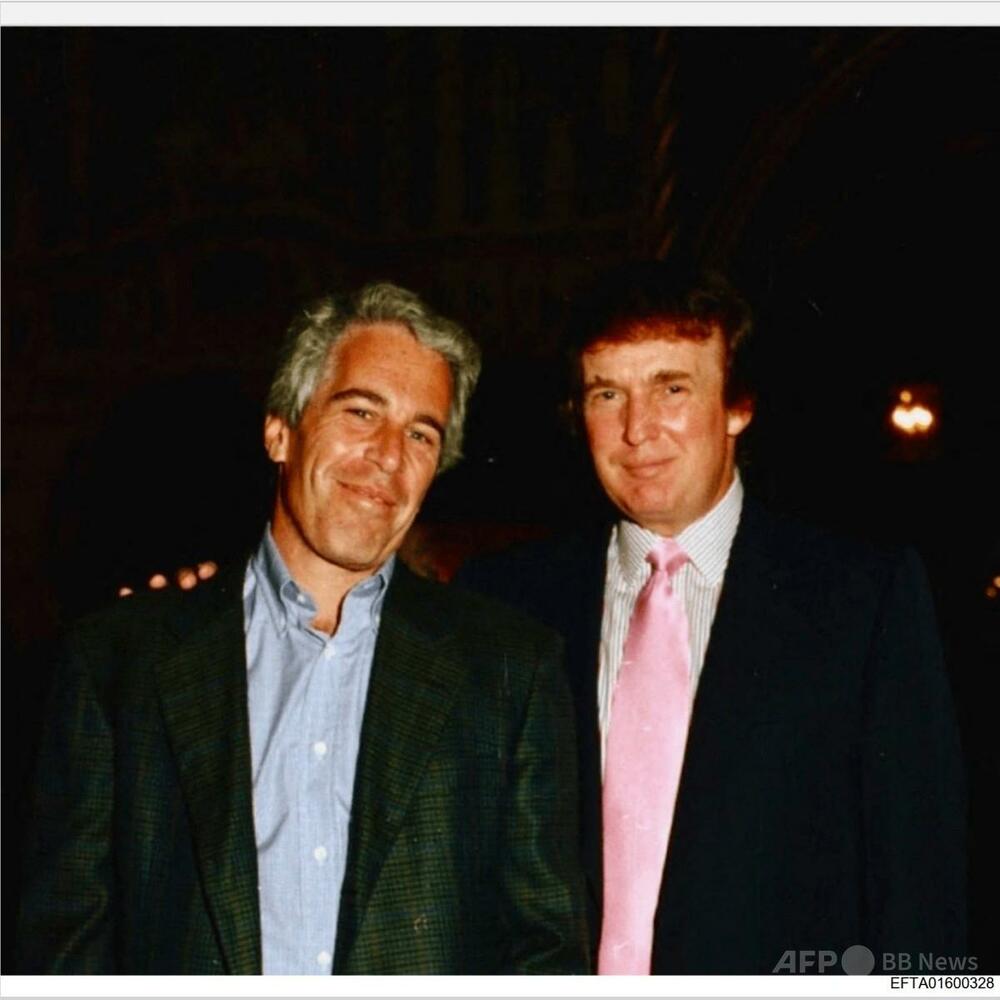2021年の自民党総裁選で、初めて複数人の女性議員が立候補している。1955年の結党以来、首相の大半を輩出してきた自民党総裁選で、過去に立候補した女性は小池百合子東京都知事のみ(2008年)だった。小池都知事は、今回の総裁選を受けて「日本にはタリバンがいないのに、何でこんなに女性の活躍が遅れてきたのか」と政治における女性リーダーの少なさを問題視している。(*1)
一方で世界に目を向けると、米国では2020年にアジアとアフリカの2つの人種的ルーツを持つカマラ・ハリス氏が副大統領になり、ニュージーランドではジャシンダ・アーダーン首相が、コロナ禍を通じて高い支持率を獲得してきた。今月のドイツ連邦議会(下院)選挙を期に引退したアンゲラ・メルケル首相は、16年にわたってドイツ、そしてEU全体を率いてきた女性リーダーだった。小池都知事が指摘するアフガニスタン・タリバン政権のように、未だ指導的立場にある女性を認めない国も少なくないが、それでも多くの国で女性リーダーの活躍が広がっていることは疑いがない。
こうした「数」の変化がおこる中で、あわせて語られるのは「質」の問題だ。たとえば高市早苗議員について、日本初の女性総理大臣が実現すれば「画期的」であるが「一部のフェミニストは反対している」と指摘されるように、どのような女性議員であれば相応しいのか?という議論も巻き起こっている。
日本における、女性政治家の現状はどのようになっているのだろうか?そして、クオータ制などで巻き起こる「数」に対する政治家の「質」、すなわち資質の問題についてどのように考えれば良いのだろうか?
(*1)この発言が適切な比較であるかは、別の問題があるだろう。
女性政治家の数
女性と政治の関係については様々な論点があるが、最もよく議題に上がるのは女性政治家の数だ。端的に言えば、日本は世界的に見ても女性政治家の数が少なく、閣僚や議員ともにG7最低レベルを維持したままだ。
まず日本における女性議員の数や割合について概観した後、その問題点を確認していこう。
国会議員
IPU(列国議会同盟)の調査によれば、日本の国政レベルの議員のうち女性が占める割合は世界第166位となっている。これは下院の割合を元にした数字となっており、日本においては衆議院の数字が反映されている。具体的には、464議席のうち女性議員は46人で、割合としては9.9%だ。
この調査における第1位はルワンダで、80議席のうち女性議員は49人で、割合としては61.3%となる。ルワンダは、指導的な立場に就く女性の数を憲法で定めている他、1990年代前半のルワンダ紛争によって男性の多くが殺害されたため、女性の社会進出が進んだという背景がある。
日本はG7の中で最低位となっており、最高位はフランスの39.5%、その他に英国は33.9%、米国は27.3%となっている。ちなみに中国は24.9%で、インドは14.4%だ。
ただし参議院を見ると、244議席のうち女性議員は56人で、割合としては23.0%となる。上院の世界平均である24.8%には届いていないものの、衆議院よりは女性割合が高い状況となっている。この背景としては、参議院選挙で導入されている比例代表制が女性候補を生み出しやすい傾向があること、2019年の参院選は「政治分野における男女共同参画推進法」が前年に成立してから初めての大規模な国政選挙で、立憲民主党や国民民主党などの野党が女性候補者を積極的に擁立したことなどがある。
とはいえ全般的には、日本の国政レベルにおいて女性議員が少ないことは間違いない。
地方議員
地方議員については、内閣府による調査がある。それによれば都道府県議会における女性割合の平均は11.4%となっており、最も高い東京都は29.0%だが、最も低い山梨県は2.7%となっており、県議員37人のうち女性はたった1人に過ぎない。
またこの調査では、市区や町村議会における女性議員の割合についても都道府県別で明らかにされている。たとえば東京都の市区議会には合わせて1,531人の議員がいるが、このうち女性は467人で30.5%だ。全国で最下位となる長崎県の市区議会には合わせて283人の議員がおり、うち女性は21人で7.4%だ。
町村議会で見ると、最下位となる青森県は合計349人の議員のうち女性は16人で4.6%となっており、島根県とともに5%未満の割合となっている。
また、市区町村議会において女性割合が10%未満となっているのは10県ある。10%以上15%未満は23道県、15%以上20%未満は7府県、20%以上は7都府県となっている。つまり都道府県の半数以上は、市区町村議会の女性割合が15%にも満たない状況だ。
他にも女性議員ゼロの市区町村議会が、全国に342も存在しており全体の19.6%を占める(2018年時点)。10%未満も411議会あり、全体の23.6%となっている。
地域によって状況は異なるが、全体としては国政レベル以上に地方自治体レベルでは女性割合が少ないことが示唆される。
政党・首長など
では、政党や首長などの政治的リーダーについてはどうだろうか?言うまでもなく、日本では未だ女性首相は誕生していない。現職閣僚の女性についても、上川陽子法務相と丸川珠代五輪担当相の2名のみであり、この割合は世界151位だ。
国会に議席を有する政党のうち、女性が現在も代表を務めているのは社会民主党(福島瑞穂党首)のみにとどまる。そして2019年の参院選直後に集計されたデータによれば、主要各党の参院議員における女性割合は以下の通りだ。
自民党 17.7%、公明党 17.9%、立憲民主党 25.0%、国民民主党 33.3%、共産党 38.5%
ちなみに今秋におこなわれる衆院選で、女性候補者の擁立目標を設定しているのは立憲民主党(30%)、国民民主党(30%)、共産党(50%)、社民党(50%)の4党のみで、与党・自民党は目標を定めていない。政党内で女性候補者や女性リーダーが生まれていくためには、まだまだ時間がかかりそうな気配が強い。
自治体の首長にも、女性リーダーは多くない。現在、47都道府県のうち女性首長は東京都の小池都知事と山形県の吉村美栄子県知事の2人だ。日本の憲政史において、都道府県知事になった女性は2000年の大阪府・太田房江知事をはじめとして、わずか7人に留まる。
市区町村についても、2019年4月時点で政令指定都市の女性市長は20都市のうち2人(10.0%)で、女性の市区町村長は1,721箇所のうち32人(1.9%)にとどまる。
また政府や地方自治体などに付随する行政機関として審議会があり、外部の民間人材などを登用して専門知識を活用する役割を負っている。法的根拠が異なるため厳密には一緒くたにすべきではないが、最近では新型コロナウイルス感染症対策分科会において、尾身茂会長の提言が緊急事態宣言などの政策決定に大きな影響を与えていることが知られる。この事例からも分かるように、審議会が与える政治的影響力は時に大きいため、そのジェンダーバランスにも注目する必要がある。
国の審議会などの委員に占める女性の割合については、第4次男女共同参画基本計画によって成果目標が定められており、目標の40%以上60%以下を2020年は40.7%でわずかに超えている。同じく審議会などの専門委員についても、30%という目標を同年30.35でわずかに超えている。
都道府県レベルで見ると平均33.3%となっており、最も高い徳島県は48.6%に達しているが、最下位の秋田県は23.6%となっている。その実情については個別に検討される必要があるが、一般論として審議会のジェンダーバランスは議員や首長などよりは是正が進んでいると言えるだろう。その背景として、具体的な成果目標が数字として掲げられたことも見逃すべきではない。
なぜ女性政治家が増加するべきか?
以上のように、政治における女性の割合はまだまだ道半ばだが、そもそもなぜジェンダーバランスに配慮される必要があるのだろうか?近年、ジェンダーの問題はますます注目を集めているが、それでも「能力のある女性が少ないだけ」論や「女性ばかりを優遇しているのは逆差別だ」論などが後を絶たない。
こうした批判に対してはジェンダーの専門家からは豊富な応答がされているが、今回の総裁選に際しても「実力ある女性が、結果的にリーダーになれば良いだけ」という声が聞かれた。そこで本記事では政治の問題に絞って、なぜ女性政治家が増加するべきなのか?について見ていこう。
政治において女性議員が少ないことの問題は、過少代表(under-representation)の問題と呼ばれ、数多くの研究がなされてきた。そこでは大きく3つの視点から議論がされている。(*2)
(*2)以下で見ていく論点は、日本国外の事例にもとづく研究や指摘を含むため、必ずしも全ての議論が日本に当てはまるとは限らない。人種や階級による政治参加の違いや、ジェンダーによる政治的立場(右派的な政治的立場の女性が優勢な国・地域もある)の差異などがある他、労働や結婚の状況によっても実情は大きく異なる。たとえば、テキサス大学オースティン校のパメラ・パクストン教授らの研究を参照。
"女性向き"政策の実現性
女性議員の増加が求められる理由として、よく説明されるのは「特定のニーズに応えた政策が、生まれやすくなるから」というものだ。分かりやすく言えば、子育てや教育、健康など特定の政策について女性議員増えることで実現可能性が上がるという視点だ。こうした政策は一般的に"女性向き"と語られることも多く、そもそもこうした政策を女性と結びつけることの問題もあるが、その問題は一旦置いておく。(*3)
たとえばマンハイム大学のゾハル・ヘサミ教授らは、地方自治体による保育サービスへの公的支援に注目して、女性議員の増加が、その支援拡大につながることを明らかにしている。具体的には、地方議会に女性議員が1人増えると、公立保育のサービスが約40%拡大するとされている。興味深いのは、この結果をもたらした要因について、女性議員による政策への賛成票ではなく、同性議員の増加によって女性議員たちが積極的に議論へと参加でき、その結果として政策決定に影響したというメカニズムが示唆されたことだ。
また途上国では、女性議員の増加が教育および健康分野で公的支出を増加させ、学歴におけるジェンダー格差の解消や乳幼児死亡率の削減などに貢献したという複数の研究をレビューした分析もある。この分析では、米国やスペイン、イタリアなどの先進国では公的支出の規模や割合に影響を与えなかったことも示されているが、従来の研究が、支出の先にある政策の結果(パフォーマンス)への影響を見落としている可能性があるとも述べられている。先進国ではすでに、一定上の支出が教育や健康に充当されているため、その支出規模ではなく政策効果に注目するべきだという見解だ。
他にも女性議員の増加が、気候変動に対してより力強い対策を講じることに繋がり、それらは因果関係であることを示唆している研究もある。加えて、議会における女性割合の増加は、対外関係にも影響を与えるという研究もある。それによれば、女性議員が増えると対外援助の総額およびGDP比率の両者が増加し、それらはジェンダー、教育、そして健康関連のプロジェクトに配分されることが多いという。援助を受ける途上国では一般的に女性の人権が侵害されやすいことを考えると、女性議員の増加は、国を超えて良い影響を生み出す可能性もあるのだ。
前述したへサミ教授らは「女性のニーズや選好が考慮されるためには、政治において女性の声を十分に反映させる必要があることを示してる」と述べる。
(*3)この問題について、名古屋大学の田村哲樹教授らは『アカデミックナビ 政治学』(勁草書房、2020年)で、女性議員が子育てや介護などの「女性イシュー」などの政策に囲い込まれ、そうした政策は経済や外交など「男性向き」の政策に比べて重要度が低いとみなされることが問題だと指摘する。女性議員の増加は、男性的な政治文化や既存の秩序 ・価値観、価値の序列自体の問い直しと併せておこなわれる必要があるという。
「代表」の正統性と民主主義への信頼
2つ目に、立法の場(議会)において女性議員が不当に少ないことは、政治的な「代表」の正統性を毀損して、民主主義への信頼を脅かすという問題がある。民主主義においては、選挙によって選ばれた議員が市民の代わりに代表者として活動する。その時、議員が市民を適切に「代表(representation)」しているかは、重要な問題となる。
LSEのアン・フィリップス教授は、有権者に約束した「理念(公約)」を実行する代表者として政治家や政党を捉える「理念(アイデア)の政治」ではなく、「誰」が代表しているかに注目する「存在の政治」の重要性を唱えた。(*4)
この視点に立つと、たとえば白人男性の議員ばかりで構成された議会は、有権者を適切に「代表」しておらず、女性や人種・民族的マイノリティの代表者である議員が、人口比に近い形で参加している必要がある。つまりジェンダーの問題に限って言えば、「代表者の男女比が均等に近いほど、その政治体制は民主的であると考えられる」のだ。言い換えれば、ジェンダーバランスが配慮されていない議会や民主主義国家は、政治に関する平等な権利が傷つけられているとも言える。
こうした問題は、理想や理念の問題としてだけではなく、実証的にも確認されている。男女別割当制度によって女性議員が増加したウルグアイでは、結果として女性の政治的関心や政治問題への理解、選挙への信頼性などが女性の間で改善したことが確認されている。
また、女性が男性と同じレベルで政治的な関心を持ち、政治的有効性(自身に政治的判断力があり、政府は市民の声を反映しているという感覚)を感じるようになれば、女性の投票率は男性よりも高くなることを予想した研究や、女性議員の増加が女性の政治的関心を高めることを示した研究もある。
つまり、女性政治家の増加が求められる理由は、女性の意見が適切に「代表されている」という感覚を熟成し、政治への関心や選挙への信頼、すなわち民主主義への信頼を高めることに繋がるからだと言える。
(*4)フィリップスらの議論に関する日本語文献としては、田村哲樹『政治理論とフェミニズムの間―国家・社会・家族』(昭和堂、2009年)や、田村哲樹ほか編『ポジティブ・アクションの可能性――男女共同参画社会の制度デザインのために』(ナカニシヤ出版、2007年)などを参照。
ジェンダー規範の解体
女性政治家の増加が求められる理由として、ジェンダー規範の解体という効果も期待できる。(*5)
今回の総裁選に際して、高市早苗議員がいわゆるタカ派の候補者であることを理由として、その素質を問うような議論が左右両方から持ち上がった。中には「名誉男性」という表現によって、高市氏がいかに「女性候補らしくない女性候補」かを指摘するような声もあった。
しかしながら、1つ注意しておくべきことは、こうした議論そのものがジェンダー規範と結びついていることだ。たとえば同じくタカ派の政治家として知られる安倍前首相が総裁選に立候補した時、その政策やイデオロギー自体が問題視されることはあっても、それらが「男性らしくない」と批判されたり、「男性だから誰でも良いわけではない」という語られ方がされることはなかったはずだ。つまり、高市議員は女性候補だからこそ政策批判とジェンダーが同時に語られる場面に直面したのだと言える。
これは高市議員に対して、本人が望むか否かは関係なく「女性議員なのだから、ジェンダー問題にも敏感なはずだ」や「男性に親和的とみなされる政策を批判するはずだ」という期待(ステレオタイプ)が勝手に向けられていることを意味している。一見すると、これは高市議員を批判する左派(リベラル)側への批判のように見えるが、そうではない。「女性候補をあれほど望んでいるのに、いざ高市氏が出てきたら批判するのか」と批判する側も、結局のところ女性候補について「女性が増えるなら誰でも良いはずだ」という「数合わせの問題」としか見ていない意味で、同じ土俵に立っていると言える。
この状況は、まさに政治におけるジェンダー規範やジェンダー不均衡の問題を象徴している。女性候補は政治の世界においてマイノリティであるからこそジェンダーについて語られることを求められ、それが男性優位社会を肯定するものであれば「名誉男性」として批判を集め、逆に否定するものであれば「ジェンダーを言い訳にして実力で勝負しない」と批判される構造になっている。これは、2020年の民主党候補指名で敗北したエリザベス・ウォーレン候補が「引っ掛け問題(trap question)」と呼んで批判した問題だ。もし選挙戦で「性差別があった」と答えれば「泣き言を言うな」と言われるが、「なかった」と答えたら数多くの女性から「どこの世界に住んでいるのか」と非難されるだろう、というわけだ。
こうした立場性を求められること自体、男性に比べて女性政治家が追加的なコストを払っていることを示している。この追加コストを無くすためには、女性政治家の数自体が増えることで、そのジェンダー規範そのものが解体される必要がある。
(*5)この問題を考える上では、当然ながら公私二元論や福祉国家批判なども考えていくべきだろうが、本記事ではわかりやすさを重視して、それらには踏み込まない。
なぜ女性政治家が少ないのか?
では、女性政治家の増加は望ましいと考えられているにもかかわらず、現実としてなぜ多くの国で、女性政治家はマイノリティなのだろうか。政治的リーダーに相応しい、実力ある女性がいないからだろうか?
たとえば国際政治学者の三浦瑠麗氏は「女性国会議員はまず実力をつけることが大切ということですか」という質問に、以下のように答える。
はい。女性がリーダーになれない、いわゆる『ガラスの天井』は私もよくわかるんです。でも戦っている時に、女性だから不利だと弱音を吐いてもリーダーの座は手に入らない。勝つための論理としては、甘すぎるんです。
しかしながら、こうした言説は「結局のところ女性に実力がないだけ」という認識を再生産する危険性があり、慎重に検討する必要がある。三浦氏が問われているのは「なぜ日本では女性の首相が誕生しないのか」だが、そもそも女性議員の数が少ない状況では、女性首相が誕生する可能性も減っていく。
そのように考えると、なぜ女性議員が少ないのか?という問題を見ていく必要があるが、これは大きく3つの方向から議論がある。
野心のギャップと構造的問題
よく指摘されるのは、女性が自分の能力と成功の可能性を過小評価している「野心のギャップ」と呼ばれる問題であり、いわば「自信のなさ」から女性は公職に就いたり議員に立候補することを敬遠する、という考え方だ。バージニア大学のジェニファー・L・ローレス教授らによれば、政治的野心のジェンダーギャップは、職業選択について真剣に考慮しはじめる高校生や大学生の頃から生まれはじめるという。
しかしこうしたデータは、注意して検討する必要がある。なぜなら、結局のところ女性が政治的野心を持たない理由は、自身のキャリアに構造的なハードルが多いことを(経験的に)理解しているという「合理的選択」の一環とみなされるからだ。
アメリカ進歩センターのジュディス・ワーナーは、女性候補者を阻む要因として複数の研究にもとづいて以下のようなポイントを挙げている。
- 現職の強さ(選挙ではしばしば現職有利だが、その現職の多くは男性である)
- 政党の指導者や大口寄付者など、候補者の選択に強い影響力を持つ人々による意向(女性はしばしば財産が不足し、大口寄付者へのアクセスを欠いているため弱い候補者とみなされる)
- 女性は、候補者として声を掛けられる可能性が低い(男女共に、第三者から勧誘されることで立候補を決めることが多い)
- 政治的キャリアは高い経済的コストを払う(そのため富が不足し、キャリアの柔軟性が効きにくい女性にとって高いコストをもたらす)
こうしたハードルの存在を学習することで、女性はますます候補者となることを躊躇し、政治的野心が低いとみなされる選択につながる可能性が高い。
ちなみに上記2つ目については、現在の有権者は女性候補にそれほど偏見を持っていないことが明らかになっている。つまり、候補者選択に強い影響力を持つ人々(ゲートキーパーと呼ばれる)は、女性候補が選挙で「勝てない」と踏むことでその選定を躊躇しているが、それは誤った認識だと言える。
同様の見解については関西学院大学の山田真裕教授も、エスノメソドロジーの知見を参照しつつ「女性の政治関心が男性よりも低く、政治家になりたいという動機が男性より弱く、結果として女性の政治家が少なかったとして、それを女性の自由意志による選択の結果であると即断してはいけない」と指摘している。
家事労働などの規範
日本の状況に絞って言えば、東京大学の鹿毛利枝子准教授らによる研究も示唆的だ。鹿毛准教授らは、日本の有権者が投票する際に性別を重視することはないものの、反対に女性候補者たちは家事労働への義務や期待される役割のために、選挙に立候補することを躊躇うことを実証的に明らかにしている。
これは、法政大学の衛藤幹子教授が指摘する複数要因のうちの1つとも重なる見解だ。衛藤教授は、都市部と農村部では後者において女性議員が少ないことに注目した上で、「農村部における根強い保守的な価値観と政治的慣習を反映している」として「公共圏は男性の空間だという日本の風潮に従って、福祉国家である日本で稼ぎ手を担っている男性の規範が、女性の政治参加を妨げている」と述べる。
こうした見解は「伝統的性別役割分業により、女性の生活が家庭中心となりキャリアが断絶されることが女性の政治領域への参画を阻む要因」だとする、京都女子大学の竹安栄子学長の指摘(鹿毛准教授らの論文でも参照されている)とも重なる。
鹿毛准教授らは、家庭や労働に関する規範が女性候補者を思い留まらせているという見解から、女性政治家を増やすためには「女性は家事労働働に従事するべきだ」という社会的な規範を変更していく必要があると主張する。
最近では、専業主婦は激減しており、共働きでありながら女性が非正規雇用(パートタイムなど)に従事するモデルが増えているため、家事労働か賃金労働かという二択に限らない問題もあるだろうが、少なくとも過少代表の要因は「女性政治家の実力」ではなく、労働市場全体の問題として捉えていく必要があることは確かだろう。
政治参加の多様性
また、ジェンダーによって政治参加の形式が異なることを指摘した複数の研究もあり、それらも女性政治家が少ない原因を示唆している可能性がある。
本記事は「女性政治家の数」という非常に限られた視点の中でジェンダーバランスに注目しているが、政治参加の形式は、必ずしも選挙への立候補や投票だけに限らない。言い換えれば、女性は投票や立候補などの政治参加ではなく、寄付や市民運動など「異なるタイプ」の政治参加を実践することで、そのことが女性候補者の増加を遠ざけている可能性がある。
たとえばバース大学のヒルデ・コフ教授らの研究は、政治参加全体でのジェンダー・ギャップというよりも、政治参加の形式によって様々なジェンダー・ギャップがあることを示唆している。男性は、政党への所属や政治集会への参加、政治家との接触を好むものの、女性は請願書への署名や政治的理由にもとづく製品のボイコット・購入、あるいは社会的・政治的グループへの寄付・募金をおこなう可能性が高いという。
またイタリアの若者を対象とした最近の研究では、公共政策の策定などを通じて政府の決定に変化をもたらす「政治参加」と、他者の支援やコミュニティへの参加などに焦点を当てた自発的な活動である「市民参加」に分けた時、男性は前者、女性は後者に参加する可能性が高いことが報告されている。このジェンダー間の違いは、自律性・リーダーシップ・支配などによって規定される「男性的な行動」と、政治的コミットメントよりも地域社会への奉仕を選ぶ「女性的な行動」というジェンダーロール(社会的に期待されている性別役割)を反映している可能性があるという。
日本の事例としては竹安栄子学長が、戦後期の鳥取県地域婦人会活動に注目しながら、活動の中心的な人物であった近藤久子について、幅広い社会運動で指導的な役割を果たしつつも「政治は男の世界」という伝統的役割意識を敏感に感じ取ることで、選挙からは一線を置いていた事例を紹介している。
ジェンダーロールにもとづく政治参加の形式という視点は、前述した「家事労働などの規範」という問題とも似ているが、「女性は政治への関心が高くない」というステレオタイプ(*4)に対して、女性が政治参加を諦めているわけではないという視点を提供する意味では、異なる問題として捉えることもできる。竹安も「政治活動の主流」に対して、社会運動を「周縁」と位置づけているが、こうした中心-周縁関係も見直していく必要があるかもしれない。
ここまで見てきたのは、主に有権者の投票行動を指す「デマンド(需要)」側の問題であり、候補者の立候補など「サプライ(供給)」側の問題とは異なる。しかしジェンダー間で政治参加の形式が異なることは、女性候補者の過少性と何らかの関係を持っているかもしれない。慎重に見る必要がある論点だが、抑えておいても良いポイントだろう。
女性が家事労働・子育て・介護などに従事させられ、その結果として資産や社会的ネットワークなどを蓄積できない状況が生まれることで、立候補以外の政治参加を消去法的に選ばざるを得ないのか、それともジェンダーロールによって選挙への立候補とは異なる政治参加を主体的に選択しているのか(それを「主体的」と呼ぶことの是非もあるが)は分からない。ただし、この問題を「政治参加」という広範な視点から捉える必要があることは間違いないだろう。
(*4)ただし、これは必ずしもステレオタイプとは言えない。たとえば日本においては過去「女性は男性より投票率は高いが政治的関心は男性より低い」ことが示されており、高い投票率の背景には義務感や動員などがあると指摘されてきた。2000年以降、こうした投票行動には変化が生まれているが、過去に一程度の妥当性があったことも事実だ。
どうすれば良いのか?
では最後に、どうすれば女性政治家が増えるのか?という問題について簡単に見ていこう。
この問題について、よく知られている解決策は制度的なアプローチだ。女性に対して一定の議席あるいは候補者を割り当てるクオータ制や、男女同数の候補者を義務付けるフランスのパリテなど、ジェンダーバランスを制度によって担保する方法は、世界中で導入されている。
クオータ制について、しばしば聞かれる批判は「政治家の質を低下させる」や「能力主義の原則に反する」というものだ。これについて、多くの研究がそうしたイメージとは異なる結果を報告している。
たとえばウォーリック大学のマニュエル・バーグ教授らの研究では、スペインにおける学歴とクオータ制導入前後の政党の得票数を見ることで、この制度が政治家の質には影響を与えないことを示している。イタリアにおいても、クオータ制の導入によって高学歴の女性議員が増加したことが研究によって示されている。またLSEのティム・ベスレー教授らは、同年齢で類似した労働市場の特徴を持つ他者と比較した収入にもとづくモデルを政治家の能力として当てはめ、クオータ制が女性政治家だけでなく、男性政治家の質を高めたことを明らかにした。
このような利点が確認されている制度的アプローチだが、バーグ教授らは、クオータ制を導入しても女性が党首や市長になる可能性は高められなかったことも報告している。つまり、制度的アプローチは万能ではないのだ。
一方、前述した鹿毛利枝子准教授らの示唆に従えば、女性政治家の増加には家事労働に関するジェンダーロールや女性の非正規雇用という労働市場のあり方を見直していく必要がある。その過程では、政治や女性政治家に対する偏見、社会全体におけるジェンダーロールそのものを解体していく必要もあるだろうが、これは制度的アプローチと鶏と卵の関係であり、両者を補完的に推進していくことが望ましいはずだ。
また最近では、お茶の水女子大学大学院の濵田真里氏らによる研究にもとづく女性議員に対する有権者からのハラスメントに関する記事が注目されているが、女性政治家が直面する困難についても解消していく必要がある。今年6月、女性議員や候補者に対するセクハラ被害について政党や国、自治体に防止策を求める改正候補者男女均等法が成立したが、地方議員の半数以上がセクハラを経験する現状では、ジェンダーバランス以前の問題が横たわっていることは明白だろう。
どのような女性議員であれば相応しいのか?
ここまで見ると、冒頭で触れた「質」の問題についても必然的に答えが見えてくる。まず、クオータ制などを導入したからといって議員の質が下がるわけではないことが実証的に明らかにされていることは、既に見てきた通りだ。学歴や収入といった政治家自身のパフォーマンスだけでなく、ある地域における人口移動率や出生率、市の予算などを分析することで、女性政治家の増加が「生活の質」にどのような影響をもたらすかという研究もある。それによれば、人口移動率に変化はないものの、出生率を大きく高め、市政の効率性を上げるという結果が確認されている。
もちろん、こうした「質」の問題は制度設計によっては悪影響が生じる可能性もあるが、それはあくまでも制度の問題であり、女性議員と議員の質がゼロサムであることを意味していない。
また実証的な議論において、議員の「質」を定量化することが、必ずしも容易ではないことにも注意する必要がある。たとえば女性議員が増加することで、"女性向き"政策が増えたとすれば、それは質の向上と呼べるかもしれないが、子育てや介護など"女性向き"政策の序列を低く見積もる価値規範があるならば、その規範自体が問い直されるべきだろう。
他にも、「代表」の正統性が高まること自体がより良い民主主義を意味すると考える人にとっては、どのような女性であったとしても、女性政治家が増えること自体が「質」の向上に資すると主張するかもしれない。政治・経済的な効果を重視するか、「望ましい民主主義」という規範を重視するかは人によって異なるだろうが、一口に「質」といっても異なる議論の位相があることに注意するべきだ。
加えて田村教授らが指摘するように、小泉チルドレンのように人気取りや数合わせのために質が低いとみなされる議員が動員されるケースは、必ずしも女性に限らないにもかかわらず、女性の問題と結び付けられることが多い点にも留意すべきだろう。「未熟な男性議員が批判や揶揄にさらされる時に、その未熟さの原因が男性であることに帰されることはない点を、問題にすることもできるはずである。 つまり、『女性であれば誰でもよいというわけではない』 論は、もっぱら女性だけに資質の有無を問うてしまっている可能性がある」のだ。
規範的なポイントを重視した場合、「女性が増えるなら誰でも良いのか」という「数合わせの問題」すらも、否定できない可能性がある。つまり、一見すると女性に対して親和的ではない政策を推進する高市氏のような女性候補であっても、その存在がより良い「代表」のあり方と「民主主義」をもたらすのであれば、それは擁護されるかもしれない。今回のケースは首相であり、複数人を前提とした議員の問題とは異なるかもしれないが、少なくとも「どのような女性議員であれば相応しいのか?」という問題は、多義的に考える必要があるのだ。







 金子侑輝
金子侑輝