8月31日、国連人権高等弁務官事務所は、中国が新疆ウイグル自治区で少数民族に対し「深刻な人権侵害を実施」しており、「人道に対する罪にあたる可能性がある」とする報告書を発表した。同報告書は、5月に実施されたバチェレ国連人権高等弁務官による同地域の訪問を受けてのもので、同事務所がウイグル問題に関する報告書を発表するのはこれが初となる。
新疆ウイグル自治区での人権侵害は2017年ごろから報じられており、「ジェノサイド(民族集団虐殺)」にあたるなどと国際的に非難されてきた。2022年北京冬季五輪で、米国などが同問題をめぐって外交ボイコットを表明したことも記憶に新しい。
他方で、中国・習近平国家主席は7月に北西部の新疆ウイグル自治区を8年ぶりに訪問した。同地域は、中国が進める経済政策「一帯一路」において、中央アジアへの玄関口として機能する中枢地帯と位置付けられており、「安定と統治がとりわけ大切となる」ことが強調された。
また国際社会からの非難をめぐっては、「人権を盾にした内政干渉は認められない」として国際社会からの強い懸念を退けている。そして、アジアやアフリカの発展途上国には、一帯一路の経済的利益を前に中国を擁護する国も多い。つまり、新疆ウイグル自治区をめぐる問題は、人権問題だけでなく、一帯一路や開かれたインド太平洋といった経済覇権争いの対立にも組み込まれている。
では、そもそも新疆ウイグル自治区をめぐっては、具体的に何が・いつから・どのように問題視されているのだろうか?
新疆ウイグル自治区とは
まず新疆ウイグル自治区に関する基本情報から整理しよう。ウイグル問題を理解するためには、新疆ウイグル自治区という土地や人口構成、歴史を知ることが鍵となる。
広大な土地、豊富な天然資源
新疆ウイグル自治区は中国北西部に位置する地域で、モンゴルやロシア、インドなど8カ国と国境を接している。
面積は中国全土の約6分の1を占め、天山山脈、タリム盆地とジューンガル盆地などに囲まれている。新疆地域は古くから「西域」と呼ばれ、中国や中央アジアの経済的・政治的に繋ぐオアシス都市が栄えた。有名なオアシス都市としては、クチャやトルファン、カシュガルなどがあげられる。
新疆ウイグル自治区(Google Map)
新疆ウイグル自治区には、石油や天然ガスなど豊かな天然資源が存在する。これまでに約40カ所の油田が発見されており、埋蔵量は中国全体の約3割を占める。ほかにも、同自治区は綿の生産地としても知られ、世界シェア22%を占める中国の綿生産のうち、88%が新疆で生産されている。
47の少数民族
新疆ウイグル自治区には、47の少数民族と漢族が暮らしている。少数民族の多くは、古くから中央アジア周辺で暮らしてきたテュルク系民族で、ウイグル族やカザフ族などが含まれる。
テュルク系民族は古くから中央アジアに暮らしてきた。9世紀にテュルク系民族の祖先にあたる遊牧民族(突厥)が西アジアや中央アジアに進出して以来、中央アジアは「テュルク(トルコ)人の地」を意味する「トルキスタン」の名で呼ばれるようになる。トルキスタンに位置するカザフスタンやウズベキスタンなど中央アジアの国々では、今でも多くのテュルク系民族が暮らしている。
新疆に暮らす人々。ドッパと呼ばれる帽子を身につけている。(liuguangxi, Pixabay)
新疆ウイグル自治区の人口を見ると、総人口(約2,585万人)のうち、ウイグル族が最も高い45%(約1,163万人)、次いで漢族が42.2%(約1,090万人)を占める。ほかにも、カザフ族やクルグズ族、タジク族、ウズベク族、タタール族などのテュルク系民族が多く暮らしている。
テュルク系民族とイスラム教
こうしたテュルク系民族が宗教的・文化的にイスラム教と結びついていることは、新疆ウイグル自治区の問題を理解する上で重要となる。
新疆に暮らすテュルク系民族の大半はイスラム教を信仰している。今でも新疆にはモスクが残り、アラビア文字表記のウイグル語が使われるなど、イスラム世界の影響が根強く残っている。
新疆ウイグル自治区カシュガル市に位置するエイティガールモスク(Lukas Bergstrom, CC BY 2.0)
テュルク系民族にイスラム教が浸透した起源は、10世紀に中央アジアで成立したカラ=ハン朝まで遡る。イスラム教を国教とするカラ=ハン朝ではテュルク系ムスリムが増加する。当時のテュルク系ムスリムはイスラム世界で奴隷として用いられたが、時には奴隷出身の軍人(マムルーク)が中央アジアに自ら王朝を立てるなど、イスラム教の影響が脈々と受け継がれていった。
中国による統治の始まり
新疆ウイグル自治区にあたる地域が中国の支配を受けるようになるのは、18世紀以降だ。
中国共産党政府から新疆に派遣された代表団, 1950年(Unknown author, Public domain)
18世紀後半に清朝の支配下となり、19世紀には「新たな領域」を意味する「新疆」と名付けられた。民族自決が高まりを見せた20世紀には、東トルキスタン共和国として独立を図るテュルク系勢力も登場したが、漢族によって鎮圧された。
1949年に国共内戦で勝利した共産党が実権を握ると、1955年から「新疆ウイグル自治区」として統治され始める。
民族政策の変化
55年以降の新疆ウイグル自治区の統治は、中国国内の時代背景に合わせて変化していく(詳細は以下関連記事)。

1966年から1976年にかけて、文化大革命による政治闘争が激化した時代には、テュルク系ムスリムの宗教や文化が弾圧された。数百に及ぶモスクが閉鎖、コーランなどイスラム教関連書物が焼かれ、ウイグル固有言語の使用も禁止された。また、テュルク系ムスリムの中心人物や宗教指導者、知識人が粛清された。
文化大革命以後の1980年代には、経済改革に必要な安定性を確保するため、思想的な同化よりも統合を優先させ、テュルク系ムスリムの宗教や文化を認める動きが増した。少数民族の中心層を体制側に迎え入れたり、宗教や文化、言語に一定の自主性が認められた。1980年代前半にはモスクの修復や、コーランをはじめとしたイスラム教関連書物の発行も進み、テュルク系ムスリムの文化的繁栄に繋がった。
しかし、1980年代終わり頃からテュルク系ムスリムは再び弾圧されていく。転換の背景は主に以下2つだ。ひとつは共産党内における強硬派の伸長で、もうひとつは、共産党が先の文化的繁栄によるテュルク系ムスリムの独立運動やナショナリズムの激化を恐れたことだ。
無神論を掲げる中国共産党
共産党が新疆ウイグル自治区に介入する背景に、一帯一路における中枢都市であることや豊富な天然資源があるのは見た通りだが、なぜそれがテュルク系ムスリムの弾圧につながるのだろうか。言うまでもなく、テュルク系ムスリムの独立運動やナショナリズムを防ぐためでもあるが、より大きくは中国共産党の宗教観や宗教政策に深く関連している。
まず一般的にイスラム教の教義では、アッラーや教典・コーランが絶対的な位置づけにある一方、中国共産党は公式に無神論を掲げており、国内で認められている宗教についても、中国共産党が指導的立場にあることを打ち出している。つまり、中国共産党によって統治される社会において、個人の行動や社会的な意思決定における最終決定権を持つのは中国共産党であり、たとえ宗教であってもその価値観・方針に従う必要があるのだ。
具体的な発言を見てみると、2016年4月に習近平は、宗教は国家の「最高利益」に奉仕し、党とその中核的価値観を支持するように作られなければならず、「天に太陽が2つ無いように、中国にも主人は2人いない」と述べている。新疆ウイグル自治区の政策に関する会議(中央新疆工作座談会)でも、テュルク系ムスリムが共産党の方針に沿った「正しい国家観、歴史観、民族観、文化観、宗教観」を持つことが強調されてきた。
つまるところ、中国共産党がテュルク系ムスリムに介入する理由は、共産党が何よりも優先される唯一の道徳的・社会的権威として認めさせるためだと言える。
宗教の中国化
そこで共産党は、イスラム教を信仰するとしても、共産党を優先させ、中国への帰属意識を高めるような信仰に変えていくために、イスラム教の中国化という手段を講じている。
イスラム教の中国化では、中国風モスクの建設や聖職者の監視に加え、「ムハンマド」「アイシャ」といったムスリムに一般的な名前の禁止、海外渡航を制限して聖地(メッカ)巡礼を実質的に不可能にする施策が実施されている。
「テロとの戦い」
しかし、共産党の介入は、テュルク系ムスリムの反発や不満を招き、時に抵抗を招いてきた。
代表的なものとして、テュルク系民族が地方行政府を襲撃したバリン郷事件(1990年)、漢族を襲撃し、1500人以上の負傷者を出したウイグル騒乱(2009年)、習近平が新疆視察時に起きた爆破テロや襲撃事件(2014年)などがある。
ウイグル騒乱後に派遣された武装警察と装甲車(Andrew An, CC BY-SA 2.0)
だがテュルク系ムスリムの抵抗や暴動は、逆に共産党が弾圧を強める口実となった。そして、弾圧を強めようとする共産党には「テロとの戦い」という国際的な流れも味方した。中国共産党は、弾圧を強めるために、テュルク系ムスリムの独立を目指す組織「東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)」をテロリストとして認定すると、2001年9月の米国同時多発テロ以降、イスラム過激派の「テロとの戦い」という流れにあった米国や国連などの国際社会も、同様にテロリスト認定に追従した(*1)。
すなわち、中国共産党による新疆ウイグル自治区に暮らすテュルク系ムスリムへの介入は、「テロとの戦い」という国際社会の大義名分を隠れ蓑にした弾圧でもある。
2014年には「テロとの戦い」が、中国の文脈に合わせることで「テロと人民との戦い」と称された。2017年には「新疆ウイグル自治区脱過激化条例」が制定され、テュルク系ムスリムに対する弾圧が強引に正当化されている。
以上が新疆ウイグル自治区の土地、人口構成、歴史だ。こうした前提知識をもとにウイグル問題の問題点を見ていこう。
(*1)一時はテロリスト認定に追従した米国は2020年にETIMのテロリスト認定を解除している。すなわち、「テロとの戦い」は弾圧を正当化するために用いられる一種の「レトリック」で、そのレトリックを民族的・宗教的背景に合わせて中国共産党が使い分けてきたことも指摘されている。
どこが問題視されているのか?
法政大学の熊倉潤准教授が指摘(*2)するように、中国共産党による新疆ウイグル自治区への介入は、主に以下5つの問題点に分類される。
- 出産制限や強制不妊、強制中絶
- 強制収容と収容施設内での思想教育、虐待、拷問、性犯罪
- 強制労働
- 徹底的な監視システム
- 民族アイデンティティの否定、漢族・中国文化への同化強制
以下では、これら5つを順に見ていこう。
(*2)同氏による『新疆ウイグル自治区-中国共産党支配の70年』(中央公論新社、2022年)は、日本語で読めるウイグルの歴史や同問題に関する最良の入門書となっている。








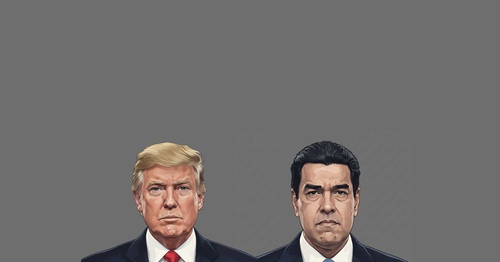



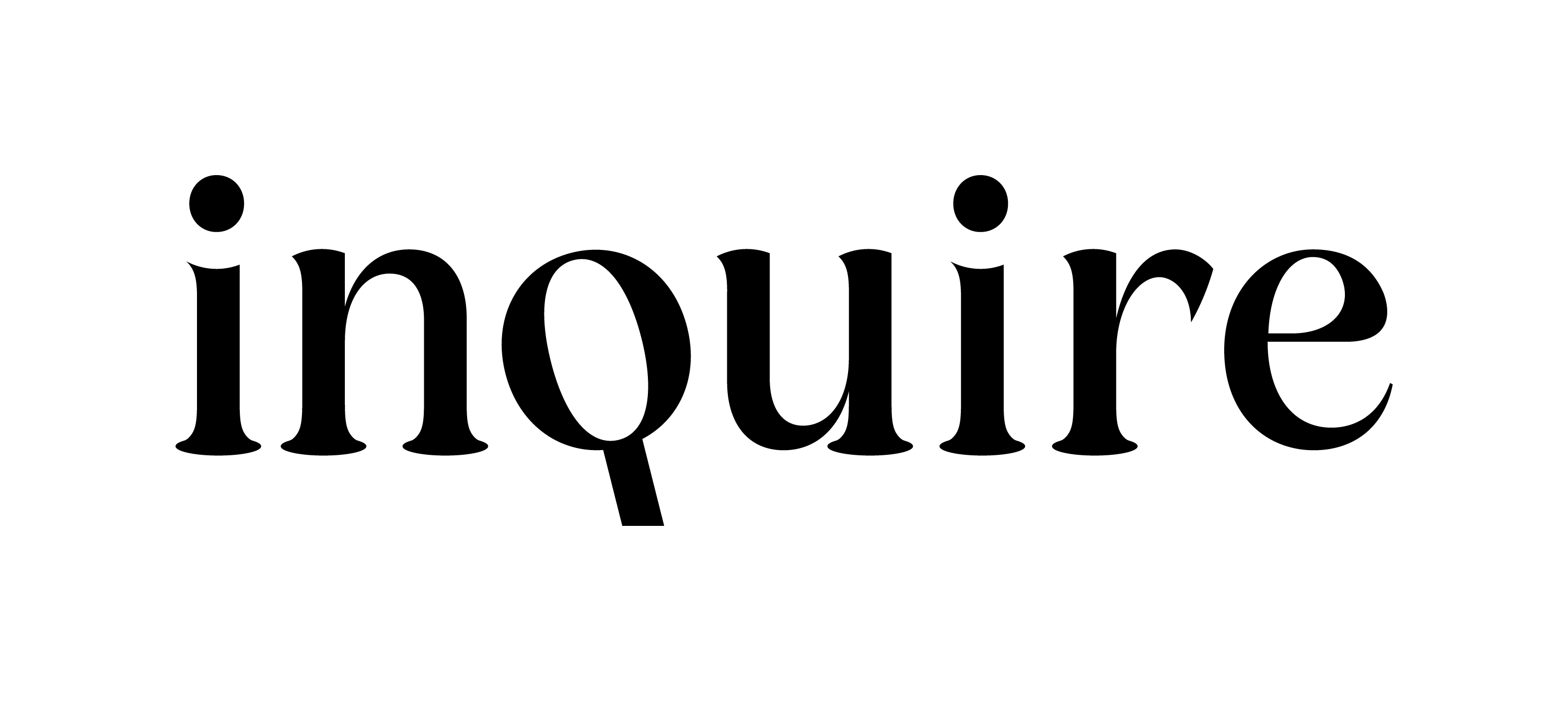












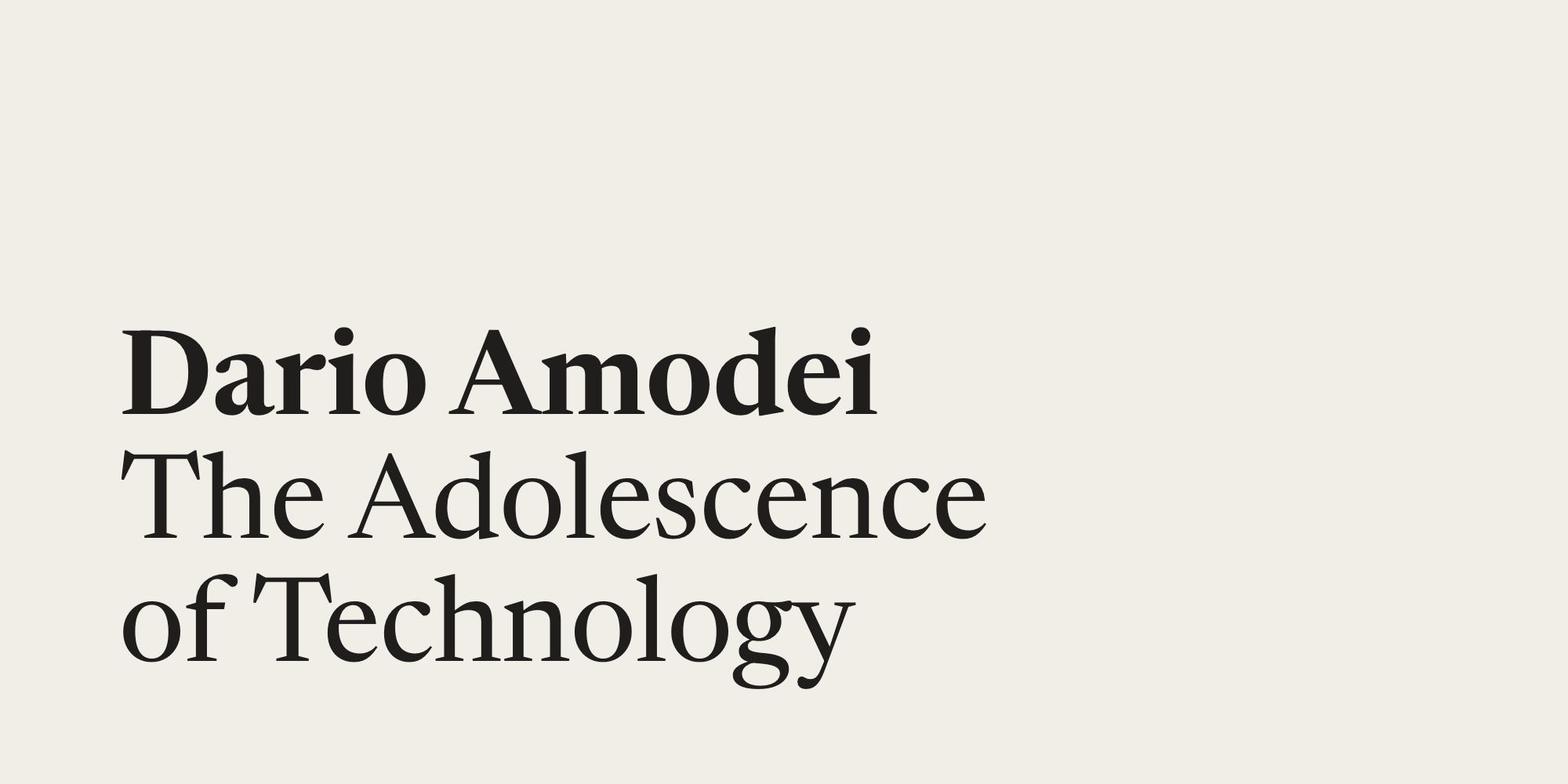
 石田健(イシケン)
石田健(イシケン)

