フードテックと呼ばれる分野に注目が集まっている。これはフィンテックなどと同様に、「フード」と「テクノロジー」を合わせた造語で、食の分野におけるイノベーションを指すとされている。
しかし、食の分野と一口に言っても、その範囲はとても広い。そこで、ここでは多様なフードテックを分類しながら整理し、盛り上がりの背景や投資の規模、そしてフードテックの成長の可能性を考えたい。
フードテックとは何か?
フードテックの1つである分子調理学を専門とする宮城大学の石川伸一教授は、フードテックを次のように定義する。
食の生産から製造、卸売、小売を経て消費者まで届き、調理して食べるという食料供給の一連の流れを「フードシステム」と呼びます。現在、この川上から川下への流れの中に多様な技術が入ってきて、さまざまな変革が起きています。その総称が「フードテック」だと捉えています。
つまり、生産から消費にいたる食にまつわる各段階を変革するテクノロジーの総称が、フードテックというわけだ。そのため、フードテックに分類される技術やサービスは非常に多い。
例えば、ゴーストキッチン(*1)やフードデリバリーなど配送や調理に関するサービスであっても、一般的にはフードテックとして分類されている。そのため、フードテックは「既存のフードシステムに対するイノベーションの総称」と考えた方が分かりやすいかもしれない。
(*1)アプリなどオンラインの注文のみに応じて、商品を調理・デリバリーする業態。Uber Eats や Doordash など、デリバリーの興隆と合わせて誕生した。
フードテックはなぜ注目されているのか?
フードテックが注目される背景は、①経済的ポテンシャル、②社会課題、③社会環境の変化 という3つの観点から理解することができる。
経済的ポテンシャル:飲食料の巨大な市場
フードテックが注目される最大の要因は、飲食にまつわるマーケットの規模がそもそも巨大であるためだ。現在、世界の飲食料の市場規模は約1,000兆円ほどと推計されている。この市場規模は今後の人口増加によってさらに拡大し、農林水産省の推計では2030年までに1,300兆円を超えるともされている。
また、日本、米国、イタリアで実施された調査によると、消費者のうち20%から30%は、現代の食に対して追加費用を払ってでも解決したい不満を抱えていると試算されている。つまり飲食料の市場は、現在の推計規模を超えるポテンシャルを秘めており、既存のフードシステムに付加価値を与えるフードテックはまさに飲食料市場の規模をさらに拡大するための駆動要因となり得る。
フードテック自体の将来的な市場規模については様々な見解があるが、2019年時点ですでに約28兆円の規模をもち、2027年には44兆円を超えるとの試算もある。この数字はそのほかのテック系市場、例えばフィンテックの市場規模予測と比較すると、2倍以上大きな数字だ。
経済的ポテンシャル:食品廃棄による経済的ロス
フードテックの経済的なポテンシャルとしては、飲食料市場におけるマスマーケティングによる経済的ロスという問題もある。
一般的に飲食料市場では、同じ商品を幅広い消費者層に提案するマスマーケティングをおこなっている。しかし同時に、大半の食品は工業製品とは異なり、賞味期限や消費期限が定まっている。したがって、在庫として保存できる期間が比較的短く、期限が到来すれば在庫は必ず廃棄しなければならない。
この廃棄がいわゆる食品ロスであり、食品ロスの発生は食品産業の収益性に大きな影響を与える。そのため、食品業界では個々の消費者のニーズを的確に把握することが収益性向上のために重要となる。
こうした需要予測のために不可欠なツールが、AIやビッグデータを導入したフードテックのサービスだ。
社会課題:環境負荷への懸念
フードシステムが抱える社会課題への対応という観点からも、フードテックへの期待は高い。








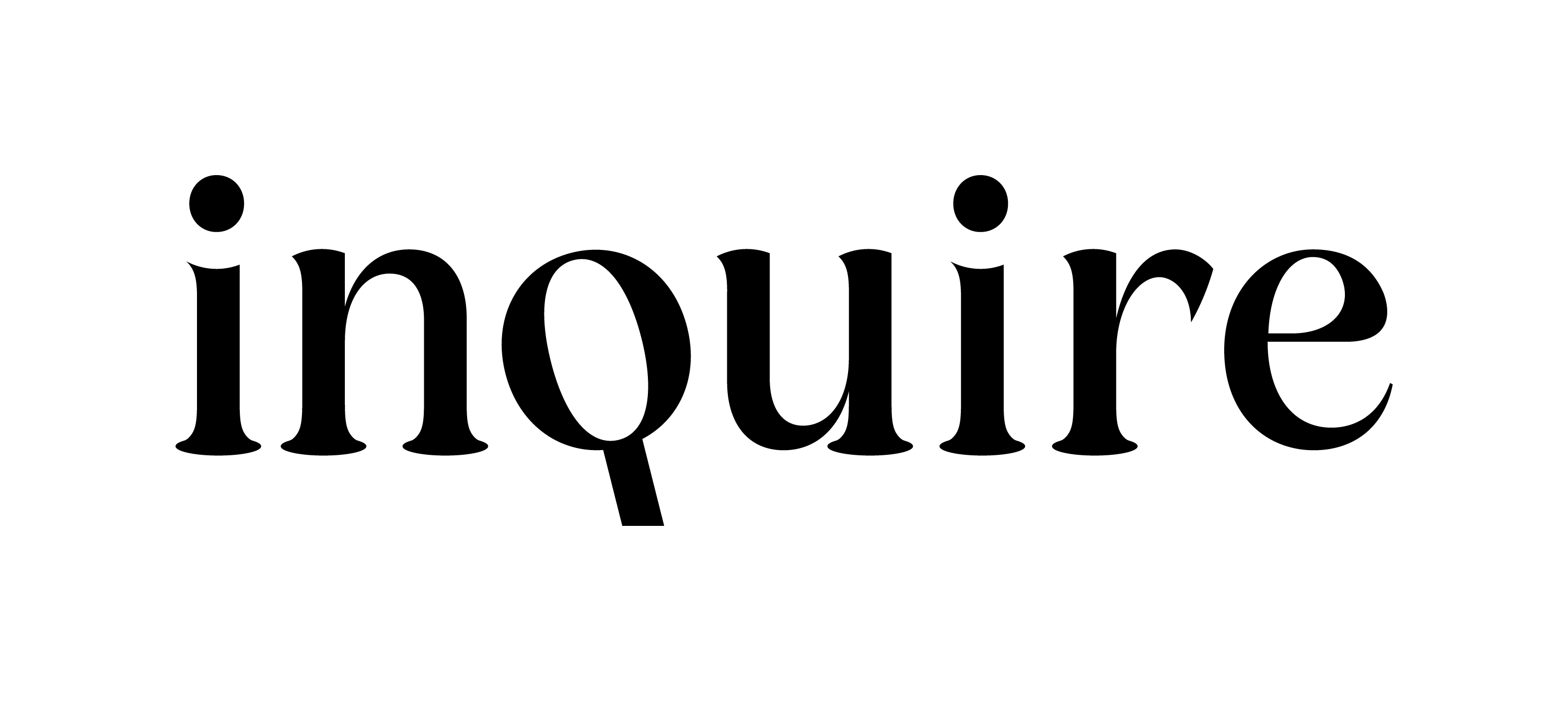










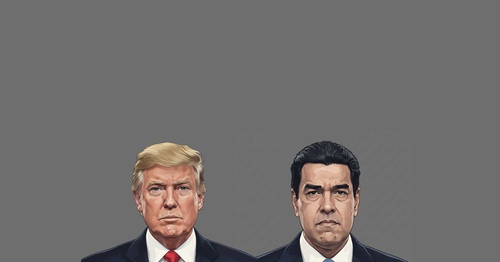



 赤羽秀太
赤羽秀太



