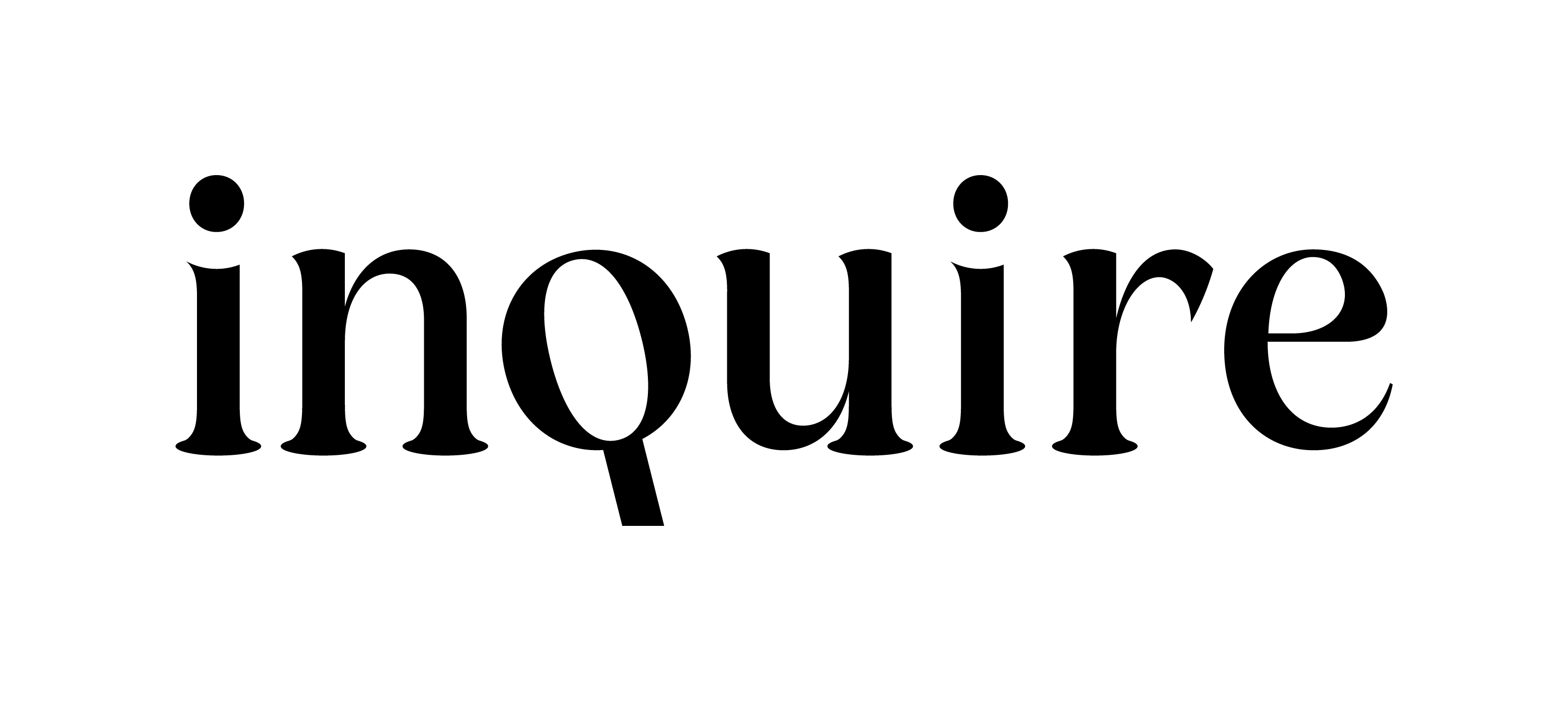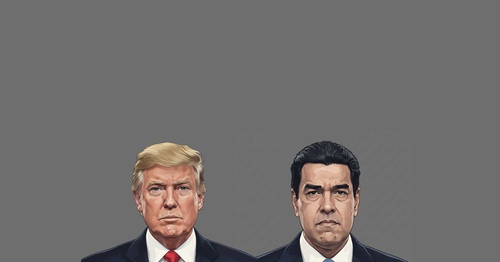インボイス制度が2023年10月にスタートする。インボイス制度とは、企業間の取引などを管理し、消費税額を正確に計算するための仕組みだ。消費税にまつわる制度変更の問題であり、法人・個人を問わず、多くの事業者に影響がある。
しかし、制度開始まで1年を切った中でも備えが進んでおらず、周知が急務になっている。また制度の変更自体に対しても、一部で強い批判が上がっており、それを耳にすることも多い。
一方、インボイス制度を理解するためには消費税や請求書に関する知識が必要であり、制度自体も複雑であることから、具体的に何が問題となっているかを理解することが難しい側面もある。
本記事ではインボイス制度について、簡潔に概要を説明した後に、その意義と限界を示すことを目指したい。インボイス制度とは何であり、どのような課題から、なぜ批判されているのだろうか?
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月から始まる、新たな消費税の仕入税額控除の方式だ。消費税を納付する時の控除(一定の金額を差し引くこと)の様式(ルール)が変わるため、広い範囲の事業者に実務的な影響があり、事業者によっては事実上の増税となるために、賛否が分かれている。
消費税の仕入税額控除とは
インボイス制度の概要を理解するためには、消費税の納付における「仕入税額控除」という仕組みを理解する必要がある。
仕入税額控除とは、ある事業者が納付するべき消費税額を計算する時に、控除として一定の金額を差し引ける仕組みのことだ。
仕入税額控除とは(筆者作成)
まず、改めて消費税が納付される流れを確認しておこう。
消費税は、商品やサービスを購入した消費者が負担し、金銭を受け取った事業者が国に納付する仕組みとなっている。ただし、その事業者も「仕入れ」として他の事業者から商品やサービスを購入しており、その際にも消費税を払っているため、消費者から預かっている消費税額をすべて納付すると、その事業者は二重に税金を支払ってしまうことになる。
そこで事業者は、「売上に係る消費税額」(=消費者から預かっている消費税額、上図であれば1,000円)から「仕入れに係る消費税額」(=他の事業者へ支払った消費税額、上図であれば300円)を差し引いた額(上図であれば700円)を消費税額として納付している。
この「仕入れに係る消費税額」のことを「仕入税額」と呼び、消費税額の計算時に仕入れ税額を差し引くことを「仕入税額控除」と呼ぶ。
インボイス制度の概要
この仕入税額控除の仕組みが新しくなるのが、インボイス制度の概要だ。インボイス制度の理解で、まず押さえておくべきポイントは次の2点だ。