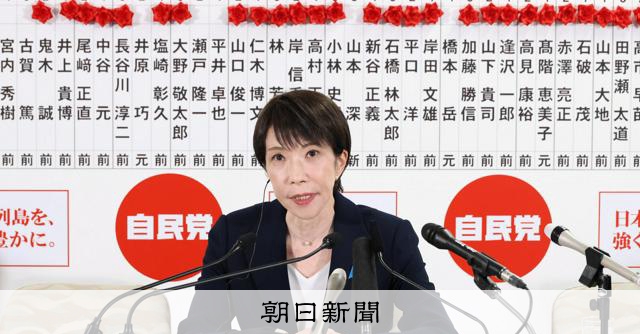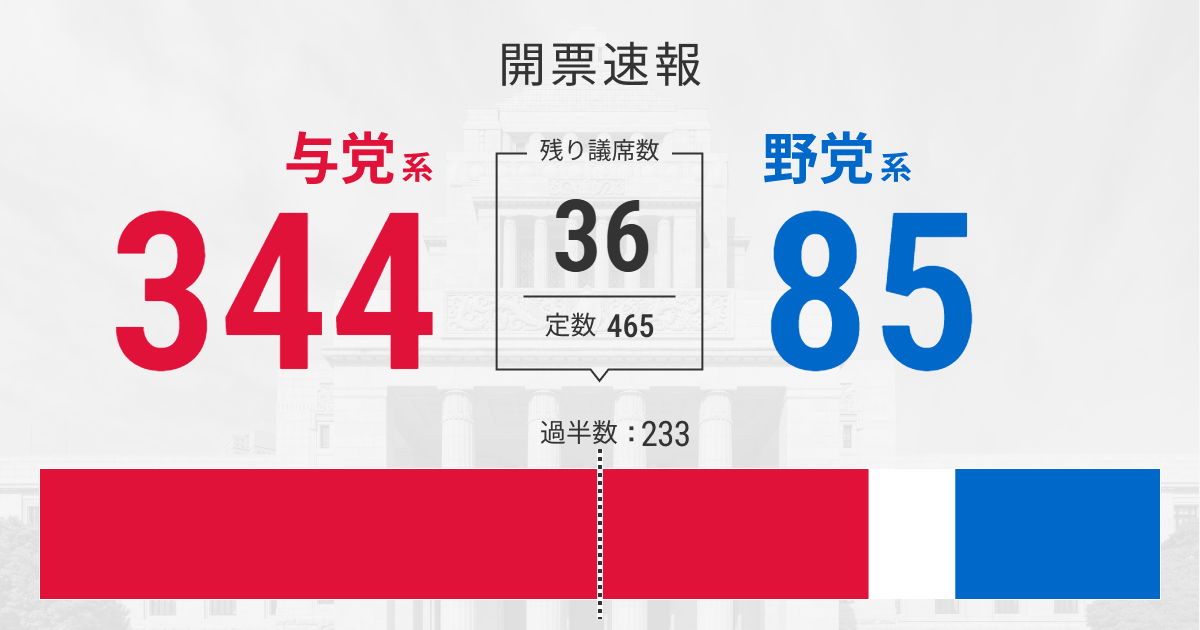今月20日、東京オリンピック・パラリンピック大会の開会式に関連して、ミュージシャンの小山田圭吾とショーディレクターの小林賢太郎が相次いで、辞任・解任となった。
20年以上前の発言・行動にもとづいて処罰が下されることをキャンセルカルチャーだと批判する声もある中、小林には解任という特に厳しい措置が課された。これについて大会組織委員会の橋本聖子会長は「外交上の問題もあり早急に対応するため解任することになった」と述べている。
一体「外交上の問題」とは何であり、なぜホロコーストの揶揄・ジョークは強く問題視されるのだろうか?
「外交上の問題」
橋本会長が、どのような意味で「外交上の問題」と言ったかは明らかではない。しかし大きく2つのポイントから注目することができる。
1つ目は、国際社会においてホロコーストに関する誤った認識や不適切な振る舞いがあった場合、すぐさま問題化されることだ。これについては大きく3つの方向性から考えることが出来るため、後述していく。
2つ目は、東京五輪開会式においてミュンヘン大会におけるイスラエル人犠牲者の追悼がおこなわれたことだ。これは、1972年9月5日に五輪ミュンヘン大会の選手村で、過激派武装パレスチナ人「黒い9月」によってイスラエル代表選手および関係者11人が人質に取られ、殺害された事件だ。これまでIOCは、開会式に「ふさわしい雰囲気ではない」と追悼を拒絶していたが、本大会ではじめて俳優・森山未來(*1)による死者に捧げるダンスと黙祷がおこなわれた。
「ユダヤ人国家」を掲げるイスラエル(*2)にとって、開会式の演出を手掛けたディレクターがホロコーストを揶揄していた過去は看過できないものであり、こうした点も「外交上の問題」に含まれる可能性がある。
(*1)森山は、2013年から1年間、文化交流使としてイスラエルのダンスカンパニーに在籍していた。
(*2)ただしイスラエルには相当数のアラブ人が居住しており、こうした呼称には批判も強い。詳しくは本誌「イスラエルとパレスチナはなぜ長年対立しているのか?」を参照。
外務大臣談話
どのような意味で「外交上の問題」と述べられたかはさておき、日本政府はこれを外交上の問題として処理している。解任当日の22日、外務大臣談話として「ホロコーストに関して報じられた東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係者による極めて不適切な発言について」が公開され、以下のような見解が示された。
ホロコーストの悲劇は人類史の中でも類を見ない残虐行為でした。小林氏の発言は、いかなる文脈や状況で行われたにせよ、極めて不適切であり、受け入れられるものではありません。また、オリンピック・パラリンピックが目指す「団結」、そして「共生社会の実現」という目標とも全く相容れないものと言えます。
これは小山田の件では見られなかった対応であり、解任のみならず政府として強い立場を表明している。特に外務大臣からの談話である点も、本問題が「外交上の問題」として処理されている証左と言えるだろう。
ホロコーストとは何か
では、この「外交上の問題」の注目ポイントのうち前者について考えていこう。すなわち、なぜホロコーストの揶揄・ジョークは、国際社会から強く問題視されるのだろうか?
このことを考える前に、まずホロコーストについて基本的な事実関係を抑えておこう。
そもそもホロコーストとは「1933年から1945年の間にナチ・ドイツ政権によって行われた、数百万人のヨーロッパ・ユダヤ人に対する、イデオロギー的かつ組織的な国家主導の迫害と大量殺人」のことを指す。ただしそれ以外にもロマ、知的障害者、反体制派、同性愛者などが殺害されたことも重要なポイントだ。
_1a.jpeg)
1944年、アウシュヴィッツ絶滅収容所に到着したユダヤ人(Anonymous photographer, Public domain)
もともとホロコースト(The Holocaust)という用語は、ギリシャ語が語源となっており「holos = 完全な」と「kaustos = 祭物(犠牲の捧げ物)」を組み合わせた単語だった。「Holocaust」として使用される場合「炎による大規模な破壊」を意味していたが、ナチ・ドイツ政権による迫害と大量殺人を「The Holocaust」と呼ぶようになり、現在の呼び名が定着した。
何があった?
ホロコーストといえば、ヒトラーという狂信的な独裁者がユダヤ人の抹殺を命じて、上司の命令に従った陳腐で凡庸な悪である部下たちが、それを実行したものと思われているかもしれない。
しかし東京女子大学名誉教授の芝健介は、「事実はそのように単純ではない」と指摘する。そもそも「ヨーロッパ社会が伝統的に抱えていた反ユダヤ主義」が背景にあるとして「一人の独裁者だけでなく、一般の人びとにもユダヤ人を嫌悪する意識が深く浸透していた」と述べる。
その上で、当初ナチはユダヤ人をドイツから「追放」することを目的としていたが、オーストリアやチェコ、ポーランドへと支配地域を拡大する中で、こうした地域に膨大なユダヤ人が居住していたことから、最終的にその政策に限界が生じていった。
そこでナチは「ゲットー」と呼ばれる特別居住区にユダヤ人を集めた後、ソ連を支配下に収めるとともに、彼らを仏領マダガスカル島やヨーロッパ東方へと追放しようとしたが、ソ連との戦争が泥沼化していくことで、その政策も困難となる。

1943年、ワルシャワ・ゲットーのユダヤ人(U.S. National Archives and Records Administration, Public domain)
こうしてナチによる場当たり的な政策は「アウシュヴィッツに代表される六つの『絶滅収容所』――ガスを用いた殺害施設を作り、大量殺戮を行うにいたる」。ユダヤ人問題の「最終解決」は、このように紆余曲折を辿りながら、最終的にガス室での殺戮に代表されるホロコーストに行き着いたのだ。
すなわち、ホロコーストは単にヒトラー個人の暴走だけで説明できず、むしろこれまで凡庸な悪としてイメージされることも多かったアドルフ・アイヒマンのようなナチの高官や「普通の人々」の協力によって成立したことなどが、最近の研究で指摘されている。(*3)小野寺拓也は、普通の人々の協力などによってナチ体制が成立(賛同に基づく独裁論)していた背景には、ヒトラーが掲げる「民族共同体」への支持があったと述べる。
芝(前掲書)は、これらの結果として生まれたホロコーストによる犠牲者は「強制収容所で亡くなった人びとや、戦争末期収容所解体後、「死の行進」の途次亡くなった人びとを加えれば、600万名は下らない」とする。
(*3)たとえばナチ研究の代表的論者であるイアン・カショ―は、上・下2巻にわたる『ヒトラー』評伝で、その個人的特質だけでなく複雑な構造的要因に注目している。
ジェノサイド
またホロコーストが問題化される上では、ジェノサイドと人道に対する罪という2つの概念に触れられることが多い。これらについても簡単に見ておこう。
まずジェノサイドは、1948年に国連で採択されたジェノサイド条約(集団抹殺犯罪の防止及び処罰に関する条約)第2条によって、以下の通り定義されている。
- 集団構成員を殺害すること
- 集団構成員に対して、重大な肉体的又は精神的な危害を加えること
- 集団に対して故意に、全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を課すること
- 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること
- 集団の児童を、他の集団に強制的に移すこと(*4)
もともとこの用語は、ホロコーストに定義と法的処罰を与えるため、ポーランド系ユダヤ人の弁護士ラファエル・レムキンが考案したもので、ナチの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判であるニュルンベルク裁判でも言及されている。(*5)
(*4)ジェノサイドのポイントとしては、集団構成員の殺害に限らず、精神的な危害や出生の防止なども含まれることだ。たとえば米国などは現在、中国・共産党によるウイグル自治区における少数民族の扱いについてジェノサイドと呼んでいるが、具体的には「同地区では人々が拷問を受け、女性は不妊手術を強要されている」と言及しており、必ずしも殺害のみを指摘しているわけではない。
(*5)ただしニュルンベルク裁判の時点では、ジェノサイドが国際法の中で定義されていたわけではなく、裁判の法的根拠にはなっていない。
人道に対する罪
また人道に対する罪は、ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で規定された。第二次世界大戦以前の国際法では、ナチの犯罪が十分に定義できなかったことから、米英仏とソビエト連邦の4カ国は、国際軍事裁判所の構成や役割、犯罪の要件などを憲章で規定して、それを元にニュルンベルク裁判がおこなわれた。

ニュルンベルク裁判(U.S. National Archives and Records Administration, Public domain)
その後、2002年に発効された国際条約である「国際刑事裁判所(IIC)に関するローマ規程」で改めて人道に対する罪は、集団殺害犯罪(ジェノサイド)と戦争犯罪、侵略犯罪と並んで定義されている。同憲章では、人道に対する罪が以下のように定義されている。
戦前または戦時中一切の一般人民に対して為された殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為、または政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為
人道に対する罪も市民への殺戮や虐待などを対象としており、一見するとジェノサイドとの違いが分かりづらいが、両者の違いについて東京大学教授の石田勇治は、以下の内容を挙げている。
- ジェノサイドが国民的、民族的、人種的、宗教的集団の4つを特定の被害集団としているのに対して、人道に対する罪は一般住民や民間人を対象としている点
- ジェノサイドは上記4集団に対して、それぞれその「全部または一部を破壊する意図」をもって行われる行為であるのに対して、人道に対する罪にはそのような限定がない点
しかし両者はいずれも、ホロコーストをきっかけとして生まれてきた国際法上の概念である。言い換えれば、ジェノサイドや人道に対する罪という現代社会における重要な概念は、ホロコーストの衝撃によって生まれてきた。
この事実を前提として、改めてなぜホロコーストに関する誤った認識や不適切な振る舞いについて、国際社会がこれほど問題視するのかを考えていこう。具体的には、大きく3つの方向からこの問題を検討していく。
現代の人権概念の起点として
まず最初に挙げられるのは、前述したようにホロコーストがジェノサイドや人道に対する罪など、現代の人権概念を定義する上でのスタート地点となったことだ。
石田勇治は、21世紀でもホロコーストやナチ・ドイツ政権の研究が重要な理由について「人権と民主主義という近代世界の普遍的な価値と制度がそこで徹底的に蹂躙され破壊されたから」だと指摘した上で「21世紀の今日、人権と民主主義が人類にとって最も尊重・擁護されるべき普遍的な価値・制度であるとすれば、それらが容赦なく粉砕された近過去の事例に目を向けることは大きな意義がある」と述べる。
こうした見解は、国や論者を超えて多くの人々が合意する共通認識だ。
二度と繰り返してはならない
19世紀末から20世紀初頭に起きたオスマン帝国によるアルメニア人虐殺や、1990年代から2000年代のユーゴスラビア紛争におけるスレブレニツァの虐殺、1994年のルワンダでの虐殺など、歴史上ジェノサイドとして非難されてきた事件は数多くある。
しかし、それらを規定する1948年のジェノサイド条約が採択されたのは「第二次世界大戦中に行われた残虐行為を『二度と繰り返してはならない』という国際社会の決意を示す」ためであり、そこで念頭に置かれたのはホロコーストだった。
こうしたホロコーストの位置づけは「二度と繰り返してはならない(Never again)」という言葉で表現される。ハーバード大学ケネディスクール教授のサマンサ・パワーは、以下のように述べている。
終戦後、米国は「人道に対する罪」への世界的な広報者として振る舞い、ニュルンベルク裁判では主導的な役割を担ったうえで、1948年のジェノサイド条約の起草に貢献を果たした。同条約は、第三者が何もせず傍観している間に、ジェノサイドが犯される歴史を「二度と繰り返してはならない」という、米国をはじめとする世界の多くの人々が共有する道徳的コンセンサスを体現したものだ。
人権概念の転換点
こうして「二度と繰り返してはならない」というキャッチフレーズは、現代社会における人権概念の転換点となった。欧州基本権機関(European Union Agency for Fundamental Rights)は、人権教育に関する資料の中で以下のように説明している。
ホロコーストについて教えることは、現代世界を理解するために不可欠な行為である。ホロコーストは人間形成にとって重要な歴史的事象であり、1948年に人権概念を一斉に見直すことになった人間の倫理的な転換点でもある。それゆえ、ホロコーストについて教える教育者は、本質的に、将来世代の価値観を形成し、人権侵害への感度を高めるよう他者を導き、そして人権の実現に貢献するよう他者に力を与えることを手助けしているのだ。
このように、国際法においても人権概念の浸透においても、ホロコーストは他の歴史的事象とは異なる特別な位置にある。人権や人道に対する罪という概念は、ホロコースト以前から存在していたが、それらは1948年以降、人類にとって普遍的な価値であると強く認識されたのだ。
後述する論点とも関係するが、ホロコーストを揶揄することは、こうした現代社会の基盤となっている人権概念への攻撃あるいは軽視と見なされるため、それは大きな批判を浴びる理由となっている。
ホロコースト否認論・歴史認識との戦い
次に挙げられるのは、戦後の国際社会がホロコースト否認論や歴史認識などの問題と戦ってきた事実だ。すなわち、ホロコーストを軽視したり忘却する動きは、戦後繰り返し立ち現れており、それらへの取り組みは国際社会にとっての使命であった。
まず、一口にホロコースト否認論といっても、その内実は幅広い。ホロコーストそのものが存在しなかったという立場から、ガス室や強制収容所の存在を否定したり、虐殺の実態を矮小化するなど様々な立場がある。しかし確実なのは、こうした主張は一次史料を広範かつ丹念に分析する歴史研究者から明確に否定されており、各国政府も誤った歴史認識に対して厳しい措置を取っている、ということだ。
たとえばドイツでは民衆扇動罪(Volksverhetzung、刑法130条)により、ホロコースト否認論には懲役3ヶ月から5年が課される。同国以外にもオーストリアやハンガリー、ポーランド、ルーマニアなどは、ナチのシンボルを掲げる行為などを禁じている。また2009年に欧州人権裁判所は、ホロコースト否認を禁じることは表現の自由を妨げるものではないという見解を明らかにしている。
欧州委員会は、以下のようにホロコースト否認論が人権概念の否定に繋がることを強く指摘する。
特に否認論は、ホロコーストの否定およびユダヤ人社会への憎悪の扇動の両方を構成しており、反ユダヤ主義の明白な発現とみなすことができる。人道に対する罪を否定したり、明確に立証された歴史的出来事の存在に異議を唱えたりすることは、科学的・歴史的研究とは言えず、欧州人権裁判所の判例でも示されているように、ユダヤ人に対する憎悪の扇動とみなされる。
「過去の克服」の困難性
各国政府による厳しい措置は、ホロコーストの惨劇を記憶し、適切に伝えることが決して容易ではないことの裏返しである。日本では、ドイツの過去との向き合い方(「過去の克服」と呼ばれる)を見習うべきだという主張が散見されるが、冷戦期の東西ドイツや、その後の統一ドイツも決して一枚岩で過去に向き合ってきたわけではない。
具体的には1970年代から1980年代にかけて、ドイツではホロコーストに関する認識や責任、補償の議論などに転換が生まれるが、その過程について石田勇治は以下のように表現する。
いうまでもなく戦後ドイツの人びとが敗戦直後から、ナチ不法の実態のすべてを精確に把握し、それにたいする自己の責任に自覚的であったわけではない。強制労働の被害補償政策が始まるまでに半世紀以上の長い歳月が流れたように、過去の不法が不法として認識されるためには、現代ドイツ社会の法意識の十分な成熟と人権感覚の成長が不可欠であった。その意味で、「過去の克服」の進展は戦後ドイツの民主主義そのものの度合いを映す鏡でもある。
実際、戦後すぐの「普通のドイツ人」にとって、ナチ・ドイツ政権は自分たちとはおよそ無関係の問題だった。むしろ戦後の苦悩と喪失に直面したドイツ人は、自らが数百万のヨーロッパ人に苦しみをもたらした加害者ではなく、ナチズムと第二次世界大戦の被害者だという記憶をつくりあげたとして、リチャード・ベッセルは以下のように記す。
ドイツ人の目から見れば、自分たちはナチズムの加害者ではなく戦争の犠牲者なのだった。この認識が実際に疑問視されるまでには、少なくとも一世代の時間を要することになる。
忘却されるホロコースト
またホロコースト否認論や「過去の克服」の困難性に限らず、忘却もまたホロコーストが直面する課題である。2018年におこなわれた調査では、ホロコーストが米国で忘れられつつあることが示された。
米国人の31%、ミレニアル世代の41%が、ホロコーストで虐殺されたユダヤ人の数は200万人以下だと考えているが、実際には600万人にものぼる。米国人の41%、ミレニアル世代の66%が「アウシュヴィッツが何であったか分からない」と答えている。また52%の米国人は、ヒトラーが暴力を用いて[訳注:非合法的に]権力を掌握したと誤解している。
このように、ホロコーストを「二度と繰り返さない」という国際社会の決意は、決して平坦な道のりではなかった。適切な歴史認識の構築や「過去の克服」の実現、そしてホロコースト否認論との戦いなどは、不断の努力によって実現される途切れることのないプロセスだと言える。
それが決して終わりのない試みだからこそ、誤った認識や不適切な振る舞いには、現在でも厳しい目が向けられるのだ。
現在性をもつ問題
そして最後に忘れてはならないのが、これは現在でもアクチュアルな(現在も直面している)問題であるという事実だ。
繰り返されるジェノサイド
まず「二度と繰り返してはならない」という国際社会の決意は、何度も挑戦を受けている。
2000年以降だけでも、北アフリカのスーダン西部ダルフールで2003年に起きた大量虐殺や、同年に起きた第二次コンゴ戦争の中で起きた虐殺(*6)、テロ組織ISISによる2014年からイラク北部シンジャール地域で起きたヤジディ教徒の虐殺、そして現在も続くミャンマーにおけるロヒンギャ虐殺(*7)など、国際社会はいまもジェノサイドを食い止められていない。
国連・ジェノサイド防止に関する事務次長兼特別顧問のアダマ・ディエンは、「二度と繰り返してはならない」という言葉は今や「何度も繰り返されている」へと変わってしまったと警告している。また国連事務総長のアントニオ・グテーレスは、アウシュヴィッツ解放75周年にあわせて「二度と繰り返してはならない」とは「ホロコーストの物語を繰り返し語ることを意味している」と述べ、現在でもホロコーストについて理解することの重要性が高いことを強調する。
(*6)同戦争に参加したウガンダについては本誌「ウガンダは、どのような政治・人権状況にあるのか?」を参照。
(*7)ロヒンギャ問題については「なぜミャンマーでクーデターが起きたのか?」を参照。
生存者
加えて、ホロコーストを生き延びた人々は、現在でも世界中で数十万人が暮らしているという事実がある。ホロコースト生存者の定義は幅広く、収容所やゲットー、ナチ占領下の土地で隠れていたユダヤ人に限るならば2016年時点での生存者は約10万人とされ、より広範囲で見ると40万人とも言われる。
生存者は、強制収容所などナチによる暴力の後にも問題に苦しみ続けた。猪狩弘美は、以下のように指摘する。
強制収容所を生き延びた人々にとって、その後の人生において看過できない出来事も多くあった。たとえば、1980年代半ばのドイツ連邦共和国での「歴史家論争」では、戦後40年ほどが経過し、ナチズムの過去との取り組みに辟易している態度が表明された。反ユダヤ主義の高まりやネオナチの台頭も幾度も見られた。イスラエルのアラブ人に対する非寛容的態度や、虐殺、殺戮が世界中で今なお行われている現状も、多くの生存者たちの感情を乱すものであった。
「被害者の抱えた苦悩について考える際には、社会的、政治的状況との関わりも軽視できない」という事実を踏まえれば、何十年前のジョークであるから看過されるわけではないことが分かる。関係者が亡くなれば、問題を忘却したり軽視したりしても良いということでは当然ないが、現在でもホロコースト生存者がいる中では、より慎重に問題が扱われる必要がある。
ホロコーストのアメリカ化
ホロコーストへの厳しい目を規定する要素の中には、現在の政治状況も含まれる。それは冒頭の「外交上の問題」に言い換えることが出来るかもしれない。
人権や歴史認識の問題に比べると相対的な重要性は低いように見えるかもしれないが、決してそんなことはない。なぜなら人権の重視や過去への反省は、理念的な問題から生まれてくるだけでなく、国家間の政治的な力関係や世論、文化などの中からも生まれてくるからだ。
そのことを表すのが「ホロコーストのアメリカ化」という現象だ。イスラエルやドイツなどEU諸国と並び、米国はホロコーストの問題に主導的な役割を果たしている。米国には現在570万人以上のユダヤ人が暮らしており、イスラエルに次ぐ規模となっている。世界のホロコーストに関する問題に強い影響力を持っているサイモン・ウィーゼンタール・センターも、カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点としている。
1981年、米国の元大統領ロナルド・レーガンは、米国ホロコースト記念評議会の設立に際して、以下のような発言をしている。
ホロコースト以前のアルメニア人の大虐殺、それ以後のカンボジア人の大虐殺、そして他の多くの集団に対する迫害と同様に、ホロコーストの教訓は決して忘れられるべきではない。
イスラエルとの関係、米国内におけるユダヤ人の数と政治的影響力など、米国特有の事情もあるものの、それでも世界の超大国が「大規模な残虐行為やジェノサイドを防ぐことは、米国の国家安全保障上の関心事であり、道徳的責任の中核をなすもの」だと述べて、その念頭にホロコーストが位置づけられている意味は大きい。
一方、記念碑や博物館、教育現場、あるいは文学や映画など大衆文化の中でホロコーストが記憶されるだけでなく、それが乱用・産業化されている現状を「ホロコースト産業」として批判的に見る動き(*8)もある。
「ホロコースト産業」への批判が、ホロコースト否認論に利用されることを危惧する声は強いものの、1978年のテレビ映画『ホロコースト』が世界のホロコースト認識に決定的な影響を与え、米国におけるホロコーストへの関心の高さが、世界に強い影響を与えていることは間違いない。加藤幸実は、以下のように述べる。
アメリカ合衆国における取り組みは、ホロコーストの「文化的記憶」の担い手として評価されることが可能であるし、誰でもホロコーストについて語る権利はある。しかし、その記憶のされ方は常に社会的チェックを受けなければならないものである。
つまり「アメリカ化」には両義的な側面があるものの、それが文化や政治、教育などでホロコーストへの関心・問題意識を高め続けていることもまた事実なのだ。「ホロコーストのアメリカ化」や「ホロコースト産業」は、人権や歴史認識とは異なる方向から、その問題の重要性を人々に想起させている。
以上のように、様々な面においてホロコーストが現在でもアクチュアルであり続けていることは、その誤った認識や不適切な振る舞いがすぐに批判を受ける土壌となっている。
(*8)この代表的な論者としては、『ホロコースト産業―同胞の苦しみを「売り物」にするユダヤ人エリートたち』のノーマン・フィンケルスタインがいる。
ホロコーストは"特別"か?
ここまで3つのポイントから、ホロコーストに関する誤った認識や不適切な振る舞いについて、なぜ国際社会が問題視するのかを考えてきた。これらと関連して2つの問題に触れておこう。それは「歴史家論争」と日本のマルコポーロ事件だ。
歴史家論争
「歴史家論争」とは、ドイツにおいてホロコーストが特別視されるあまり、ナチのその他の問題や現代のジェノサイドなどが軽視されたり、冷静に分析されていないと歴史家エルンスト・ノルテらが主張したのに対して、哲学者ユルゲン・ハーバーマスがそれを厳しく批判したことにはじまる。(*9)
ノルテは、ナチの問題を「過ぎ去ろうとしない過去」と述べて、ホロコーストを矮小化するものではないと断りつつも、ドイツにおいてホロコーストが神話化されていることを危惧した。(*10)一方、ホロコーストをソ連のスターリンやカンボジアのポル・ポトによる大虐殺と比較して、相対化することを危険視する声は強く、またノルテの議論自体も誤った認識に立脚していると批判を受けた。
石田勇治、以下のように問題の顛末を述べる。
歴史家論争では、ナチズムやホロコーストの相対化だけでなく、東方の脅威からドイツを防衛するためには対ソ戦はやむを得なかったとする主張や、ボリシェヴィズムの脅威を強調することでアウシュヴィッツを免責しようとする主張が右翼知識人によって展開されたが、いずれも「批判的歴史学」の厳しい批判を受けて学問的には退けられた。
その上で、ノルテらについて「決して自覚的な反ユダヤ主義者でも、ホロコースト否定論者でもなかったが、かれらの主張にナチ時代のドイツを『脱犯罪化』する、つまりナチ時代の犯罪性を希釈化する意図があったことは否めない」とする。
歴史家論争を見ても分かるように、ホロコーストにはその特殊性を強調する見方と普遍性を強調する見方がある。「二度と繰り返してはならない」という言葉には、ホロコーストが繰り返されることを懸念している意味で、普遍性が念頭に置かれているものの、一方で普遍性を強調しすぎると、ホロコーストの惨劇が相対化される危険性がある。
なぜホロコーストの揶揄・ジョークが強く問題視されるか?が問われる時、こうした両義的な立場について、過去に議論がなされてきた事実は抑えておくべきだろう。
(*9)議論の全体像については、ハーバマス『過ぎ去ろうとしない過去―ナチズムとドイツ歴史家論争』人文書院、1995年
(*10)ノルテは歴史修正主義者として非難されるが、ホロコースト否認論でも修正主義という言葉が用いられる。またノルテは、フランスの歴史家であり修正主義者フランソワ・フュレとの往復書簡でも知られるが、ここでの「修正主義」という言葉はそれぞれ異なる含意があるため、混乱を避けるため本記事では意図的に避けている。
マルコポーロ事件
日本のマルコポーロ事件とは、文藝春秋の雑誌『マルコポーロ』1995年2月号の記事に、ホロコースト否認論が掲載されたことで、同誌が自主廃刊となり、当時の社長・編集長が辞任・解任となった問題だ。当時、サイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)が同誌に強く抗議し、日本国内でもマスコミが大きく取り上げたことで、この問題およびホロコースト否認論に広く関心が集まった。
今回の小林の解任とマルコポーロ事件について、秀明大学助教の衣笠太朗は以下のように指摘する。
ラーメンズの「ユダヤ人大量虐殺」ネタ、90年代後半発表というのは偶然でないだろうね。95年にはマルコポーロ事件があり、ホロコースト否定論が本格的に日本に上陸したが、雑誌はSWCの介入で潰された。「ネタにできないホロコースト」というイメージに反抗してラーメンズはこのネタを作ったのだろう。
その上で、過去のツイートを参照しながら衣笠は「記事の十分な検証と批判なしに休刊となってしまうことで、批判者の声が単なる言論弾圧としてみなされてしまう」ことを危惧すると述べる。
すなわち、ここまで見てきたような人権概念の問題やホロコースト否認論、歴史認識の問題などについて日本国内で十分に周知・理解されないまま、反対に「ネタにできないホロコースト」という規範(コード)だけが広まり、それがマルコポーロ事件によって強化されたという懸念だ。
この構図は、今回もホロコーストの揶揄・ジョークの問題点などが十分に周知されないまま、「外交上の問題」として扱われて即時解任に繋がったことで、再び繰り返されてしまった。(*11)
本記事では、日本におけるホロコースト否認論や歴史修正主義に関する議論に触れることは出来ないが、この問題を考えるためには、日本でも90年代後半から続く、歴史認識に関する諸問題について理解しておく必要がある。ホロコーストの特殊性の問題に限らず、日本で歴史修正主義や歴史認識が語られる上での、固有の文脈・問題点について目を配ることが重要なのだ。
(*11)こうした問題については、本誌「キャンセルカルチャーとは何か?五輪開会式におけるクリエイターの辞任は「行き過ぎた対応」か」や「ポリティカル・コレクトネスの時代とその誤解:なにが「ポリコレ疲れ」を生んでいるのか?」などを参照
なぜホロコーストの揶揄・ジョークは強く問題視されるか?
ここまで様々な視点から、なぜホロコーストの揶揄・ジョークが強く問題視されるか?という問題を考えてきた。具体的には、ホロコーストが現代の人権概念の起点であること、ホロコースト否認論や歴史認識からの挑戦に各国はいまでも戦い続けていること、そして様々な意味でアクチュアルな問題であることという3つの方向性から検討してきた。
もちろんこれらの論点が全てではないが、こうした事実を踏まえるとホロコーストが理由なく「ネタにできない」という規範(コード)を持っているのではなく、その扱いが慎重になるべき必然性があることが分かるだろう。
最後に、それらを踏まえた個人的な見解を述べておこう。
ホロコーストの揶揄・ジョークを強く問題視させる要素は数多くあるが、重要なことはホロコーストについて考えたり発言するには、その膨大な研究を踏まえる必要があるということだ。ホロコーストへの関心の高さから、現在でも多数の研究が出ている一方、書店などで手に取ることができる書籍は混合玉石だ。そのため、ホロコーストを軽視するような書籍や記事などに出会って、そこから誤った矮小化・相対化をおこなってしまうリスクもある。
このことを考えると、ホロコーストを揶揄したりジョークにすることは言うまでもないが、持論を語ることすらも決して容易ではない。なぜなら、その持論が立脚しているホロコースト認識が誤っていたり、現在の研究では否定されている可能性もあるからだ。
ただしこれは、「腫れ物に触るようにしてホロコーストを語るべきだ」ということを意味するわけではない。むしろ、望むべきは逆である。多くの人にとって「なぜホロコーストの揶揄・ジョークが強く問題視されるのか?」は、十分に周知・理解されているとは言い難い。だからこそ、「炎上するから」や「批判されるから」ではなく、その問題を根本的に考えていくことの重要性は大きい。
では一体、どのようにそれをおこなうべきなのだろうか?個人的には大きく2つのステップをおすすめしたい。
まず1つは、何はともあれホロコーストについては「人権と民主主義という近代世界の普遍的な価値と制度がそこで徹底的に蹂躙され破壊された」(前述、石田勇治)事実を大前提とすべきだろう。知識と経験のある信頼できる専門家の立場に立脚することは、何も思考停止を意味するわけではない。その前提を理解することで、はじめて学びの準備が整う。
その上で、自身の考えを深め、学びを広げていくために以下のような書籍に目を通すことが望ましい。
先ほど「膨大な研究」と述べたが、それらをすべて追うことは現実的ではない。しかし、ここで紹介しているのは全て日本語文献であり、多くが新書として手軽に読める形式となっている。これらを入り口に、現代の人権概念の転換点となったホロコーストについて学びを深めることは可能だろう。
- 芝健介『ホロコースト ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌』中公新書、2008年
- 石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ 』講談社現代新書、2015年
- ウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国 ある独裁の歴史』小野寺拓也訳、角川新書、2021年
- リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949 - 民族と人種の戦い』大山晶訳、中公新書、2015年
- アンネッテ・ヴァインケ『ニュルンベルク裁判』 板橋拓己訳、中公新書、2015年
- 石田勇治『過去の克服』白水社、2014年
「二度と繰り返してはならない」というキャッチフレーズへの実感を持つためには、まずこうした学びのプロセスが重要となるはずだ。ホロコーストおよび、それを国際社会がどのように記憶・継承し、補償や教育をおこなってきたかを知ることは、現在でも重要な意味を持っていることは間違いない。
(*)本記事については、衣笠太朗秀明大助教(中東欧近現代史)よりアドバイスおよびコメントを頂いた。ただし本記事の内容について、全ての責任は執筆者の石田健に帰する。