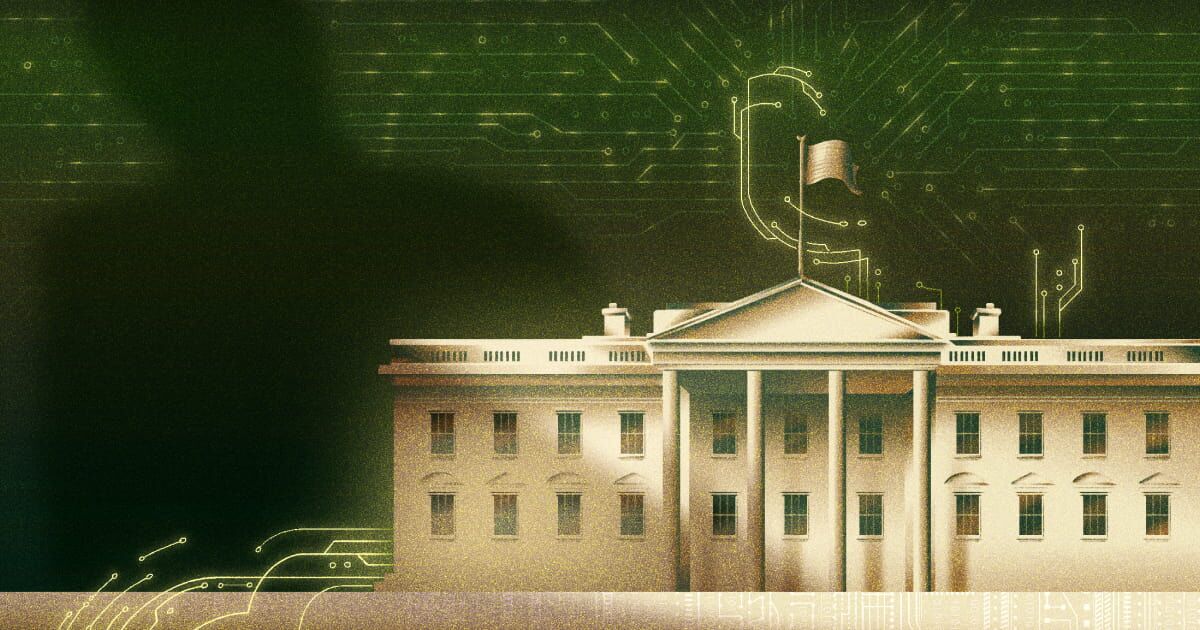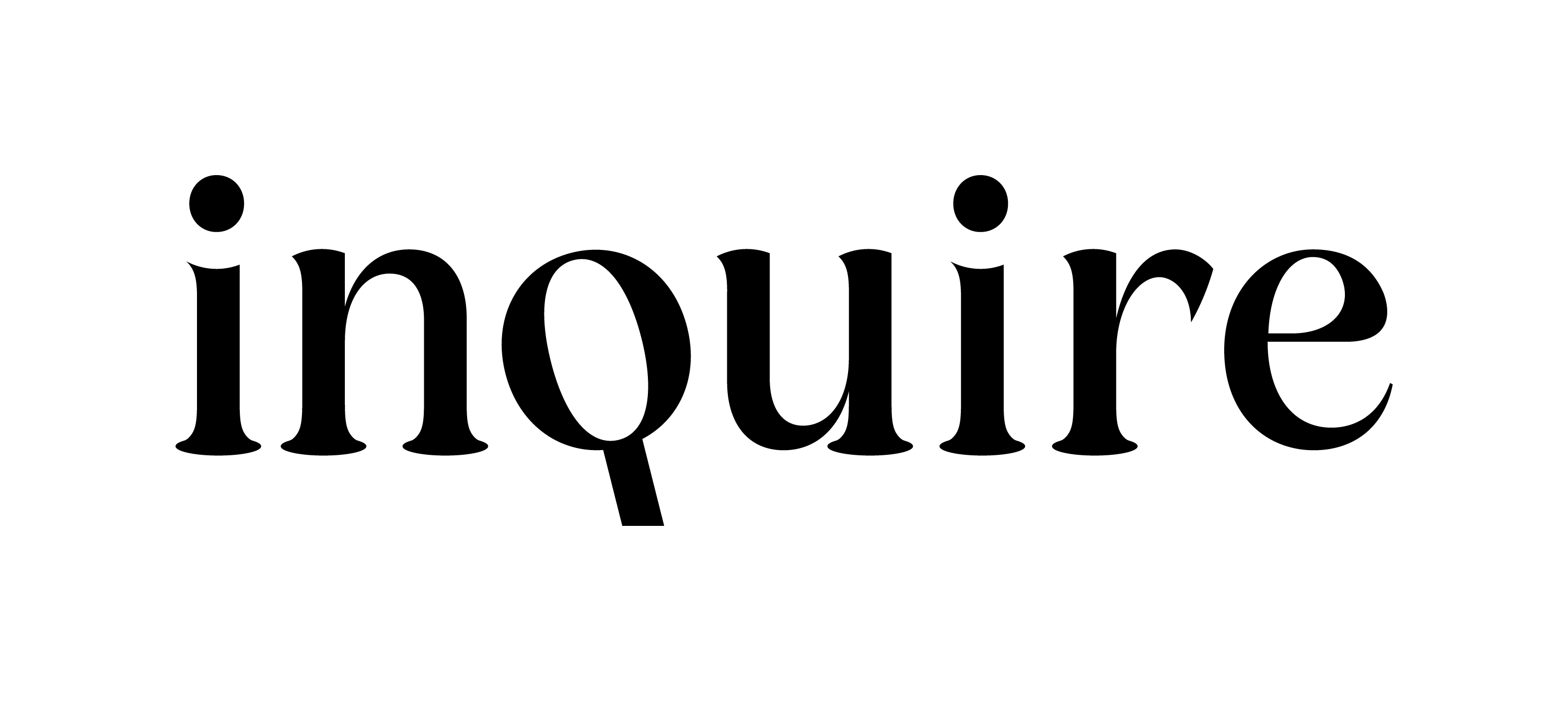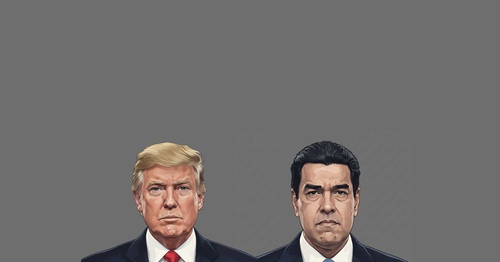推進派は「GAFAの支配からの脱却」や「デジタル資産の可能性」を謳い、反対派は「分散型技術の実用性の低さ」や「詐欺・投機的な動き」を糾弾するなど、Web3という概念に対する毀誉褒貶は激しく、これまでにも様々な議論が戦わされてきた。
実際のところ、Web3は技術的なトレンドとしてどこまで革新的であり、ビジネスの可能性として何を生み出すのだろうか?Web3に対してこれまで寄せられてきた批判を概観し、また、同時にどのような回答がなされてきたのかを見ていこう。

1. 経済構造
Web3への批判は、大きく①その経済構造に対するもの、②オペレーション上の困難さに対するもの、③消費者保護に関するものに分けられる。
ひとつめの経済構造で問題になるのは、VCのトークン保有と、プラットフォーマーへの依存の2点だ。
VCのトークン保有
経済構造の問題として示される批判のひとつ目は、VCによるトークン保有に対するものだ。
投資家であるベンチャーキャピタルが、Web3に大量の資金を注ぎ込み、資金と引き換えに過度のコントロールを手にしていることについて、「分散化」というWeb3の理念に反しているという批判がある。
VCのGAFA化?
Web3の世界では、ビッグ・テックに独占された個人情報やデータが分散化によって市民の手に取り戻されることは、重要な理念の一つだ。Web3の旗振り役であり、著名ベンチャーキャピタルのAndreessen Horowitz(a16z)でゼネラルパートナーを務めるクリス・ディクソン氏は、分散化が重要な理由について、「政府の検閲に抵抗するためでも、リバタリアン的な政治的立場でもない」と述べて、ビッグ・テックのプラットフォームが強すぎることが問題の中心にあると指摘する。
ところが、一見Web3の理解者であるように見えるa16zのようなVCこそが、分散化というWeb3の理念に反してしまっているという批判がある。これは、ベンチャーキャピタルがWeb3スタートアップに大量の資金を注ぎ込み、多くのトークンを保有することで、Web3の業界において強い影響力を持つ存在になった(*1)ことに起因している。
トークンは通常、Web3プロジェクトのガバナンスに関する議決権の役割を果たす。VCがトークンを大量に保有すれば、プロジェクトの運営をコントロールできるようになり、実質的に(ユーザーではなく)VCがそのプロジェクトを所有する状態になるためだ。
こうした状況は、そのプロジェクトが単一企業ではなく、ユーザーからなるコミュニティによって分散的に所有されるというWeb3の理念と矛盾する。
(*1)Redpoint Venturesのトーマス・トゥングズ氏によれば、Web3組織の資金調達におけるVCのトークン保有割合は、近年徐々に高まってきている。クリプト黎明期にはWeb3プロジェクトの創業メンバーやVCなどの投資家が保有するトークンは20%に抑える(残り80%はコミュニティに配分する)という慣例があったが、昨今のプロジェクトにおいては、投資家がトークンを保有する比率が増え、コミュニティへの提供割合が少なくなっている。








 赤羽秀太
赤羽秀太